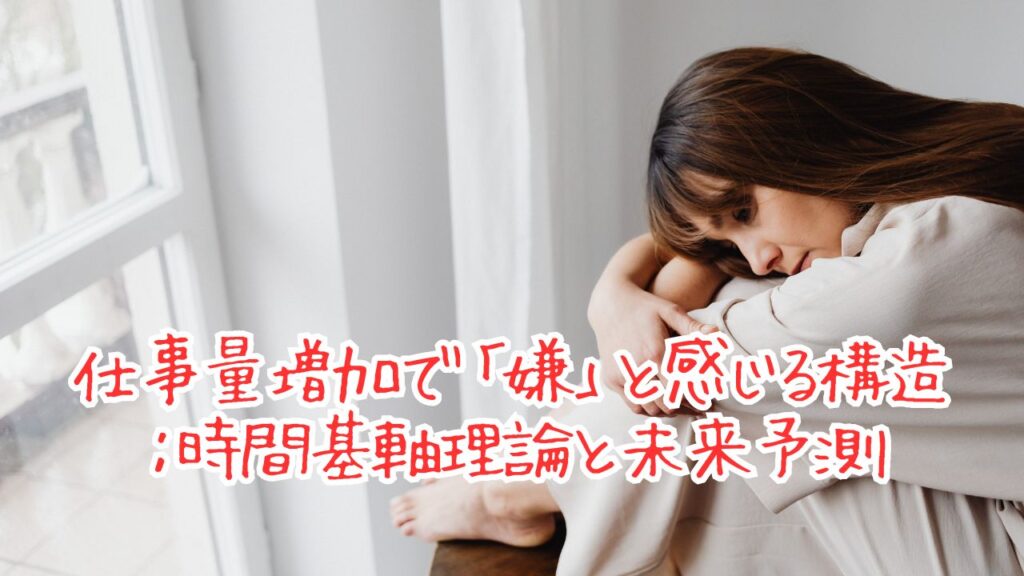
書き殴った文章をAIに整理してもらった。
目次
🧐 仕事が増えると「嫌」なのはなぜか?:時間基軸理論と感情の発露
1. 仕事が増えることへの賛否両論と動機
仕事量が増加することに対する受け止め方は、個人の状況や価値観によって異なります。
🔹 ポジティブな側面(嫌ではない例)
- 収入の増加: 残業代が出る職場では、残業によって収入が増えるため、仕事の増加を容認する、あるいは歓迎する場合がある(ただし限界はある)。
- 自己肯定感・価値観: 過去の筆者のように、「忙しくしていること=かっこいい」といった価値観や、仕事をしている自分自身に満足感を覚える時期がある。
🔸 ネガティブな側面(嫌である主な理由)
- 金銭的なメリットの欠如:
- みなし残業や管理職待遇(特に、昇進の席が詰まっている会社での形だけの管理職待遇)の場合、残業しても残業代が出ない。
- メリットがないため、仕事が増えてもモチベーションが上がらず、残業をしたくなくなる。
- 将来の不確実性: 将来の昇進に繋がる可能性があっても、それが確約されていないため、モチベーションを維持するのが難しい。
2. 「嫌な気分」の正体:時間基軸理論による考察
仕事が増えることによる「嫌な気分」は、時間の喪失を予測することに起因し、その度合いは失う時間によって比例するという考え方です。
⏳ 時間喪失のデメリット
- 仕事が増えることで、本来「仕事以外」に使う予定だった自分の時間が減る(時間喪失)。
- この時間喪失が、仕事が増えることの主なデメリットとなる。
⚖️ 失われた時間の「価値」
- 失う時間の量は、嫌な度合いに比例する。
- 「価値の高い」予定(多くの時間を投入しなければ得られないもの、例:貴重なコンサート)が潰れると、より嫌な気分になる。
- 失われた時間の量や価値が大きいほど、嫌な気分は強くなる。
🧠 感情の発露と未来予測
- 人間は無意識のうちに、その仕事で**「どれだけ時間が失われるか?」という未来予測**を行っている。
- この**「失われると予測される時間」の差分**(予想よりも時間がかかる)が、「嫌だ」という感情として発露する。
- 例: コンピュータは予測処理時間が出ても何も感じないが、人間は「あー3時間もかかるのか」と感じ、予想より長ければ気分が下がる。
3. 幸福・快楽と時間の関係性
幸福や快楽といった感情も、時間が影響しているのではないかという考察です。
⚡️ 快楽がネガティブに捉えられがちな理由
- 快楽は長時間続かない(短期的である)という特性を我々が知っているため、一般にネガティブに捉えられがちである。
📉 短期的なものへの重き
- 快楽を続けると(例:ドラッグ)、将来廃人になるという遠い未来予測ができるため、多くの人は手を出さない。
- しかし、いざ溺れると止められないのは、遠い未来(廃人になる)よりも、近い未来(すぐに快楽を得られる)の達成時間が短い方に、人間は重きを置く傾向があるためではないか。
- この「時間が短い方に重きを置く」という特性が、人間の根底に備わっているのではないかと筆者は考えている。
以下、AIにまとめて貰う前の原文
仕事が増えると、なぜ嫌なのか?
当たり前のように思えて、意外とそうでもない場合もある。
例えば、残業代がでる職場の場合、残業することで収入が増えるから、仕事が増えても良いと考えている人もいるだろう。
もちろん、限界はあるけれど。
また、自分の場合、若いときに、めちゃくちゃ仕事をしたかった時期がある。
それは、仕事をしている自分が好きだったというか、忙しくしていることが、かっこよいと思っていたというか、そういう価値観だった。
だから、オールで飲んだ朝とかに、始発の電車とか待ちながら、ノートPCを開いて、そこでメールチェックして返信書いたりして、そういう自分に酔っていた感じ。
で、そういう特殊な例を除いていくと、基本的に仕事が増えるのは嫌なものではないかなと思う。
自分の場合、みなし残業の職場も多く、残業しても残業代が出ない職場が多かった。
また、管理職待遇になると、たとえ課や部の長で無かったとしても、残業代がでなくなる。
管理職待遇というのは、まあ、年齢的に、そういう形にしないと問題がでるというか、でも、上は席の数が決まっていて、そこが詰まっていて昇進もさせられないような会社で、よくあるケース。
そういう場合も、残業しても何らメリットがないので、残業をしたくない。
仕事が増えてもメリットがない。
だから、仕事が増えると嫌になるんだろうなと。
もちろん、将来の昇進に繋がるなら、モチベーションも保てるとは思うが、昇進が確約されているわけではないので、なかなかモチベーションを上げるのも辛い。
で、この嫌な気分というのは、一体何なのか?というのを少しだけ掘り下げみる。
具体的に言えば、時間基軸理論と、感情の発露という点。
まず、与えられた仕事を時間内に収めることができれば、自分の時間は減らない。
仕事が増えると、本来仕事以外で使う予定であった自分の時間が減る。
この時間喪失がデメリットである。
なぜ、時間に着目するのか?というと、嫌な度合いは失う時間にある程度比例するのではないか?と考えているため。
もちろん、他に予定があって、それが潰れた場合は、より嫌な気分になるだろう。
それは、時間基軸理論的にも正しい。
その予定が貴重なものであればあるほど価値は高い。
貴重というのは、より多くの時間を投入しなければ得られないということだ。
例えば、牛丼を食べに行くという予定と、好きなアーティストのコンサートに行くという予定では、当然、好きなアーティストに行く予定の方が、より多くの時間を投入しないと得られない。
つまり、好きなアーティストのコンサートの方が価値が高いということ。
さて、話を戻すと、失われた時間の量や価値が大きければ大きいほど、嫌な気分になり、それは比例するというは、なんとなく感覚として理解いただけると思う。
この時、我々は、未来予測をしている。
この未来予測は、どれだけ時間が失われるか?という予測である。
そして、その失われると予測される時間の差分が、感情として発露するのではないか?というのが、今回の本題。
逆に言えば、単純に仕事を増やされても、未来予測ができていなければ、感情は発露しないのではないか?ということだ。
一番わかり易い例で言えば、コンピュータがある。
大量の計算をコンピュータにさせる場合、コンピュータは何も感じない。
ただ、処理をするだけである。
予測処理時間が出たとして、コンピュータは何も感じない。
ただ、淡々と処理するだけである。
しかし、人間は予測処理時間が出た時に、あー3時間もかかるのかあと、思ってしまう。
その時に、予想よりも処理に時間がかかるようであれば、ちょっと気分が下がるし、逆に予想よりも処理に時間が短ければ、ちょっと嬉しい気持ちになる。
そして、これと同じことが、人間の脳内で行われているのではないか?という話。
我々は無意識のうちに、時間を計算しているのではないかなと、個人的に思っている。
すべての物事ではないにしても、明確な数値が出ているわけではないとしても、感覚的なもので予測時間を出しているんじゃないかなと。
また、話がちょっと変わるけれど、幸福も時間が影響しているのではないか?と思っている。
幸福と一緒に語られることが多い言葉に、快楽がある。
快楽は一般的にネガティブに捉えられがちな気がしているが、それは快楽の時間が短いからではないか。
これは快楽の特性、つまり、快楽は長時間続かないことを我々は知っているため。
実際に、快楽を続ける方法はある。
例えば、ドラッグなどで。
しかし、快楽はすぐに慣れてしまい、量が増え、廃人になってしまう。
そのような未来予測ができるから、ドラッグをやらない人が多い。
だが、いざ快楽に溺れてしまうと、止めようがない。
それは、廃人になるのは遠い未来で、ドラッグを続け快楽を得られるのは近い未来だからではないだろうか。
遠い未来は、到達するまでに時間がかかる。
近い未来は、到達するまでの時間が短い。
そして、人間は時間が短い方に重きを置く傾向にあると個人的に考えている。
これは、トロッコ問題を時間基軸理論で考えてみるでも書いたこと。
で、そのような価値観というか、考えというのが人間の根底にあるのではないかと個人的には思っている。
快楽だけでなく、短期的なものはあまり良くないとされているのは、そもそも人間に備わっている特性なのではないだろうか。
皆さんはどう考えるだろうか?
