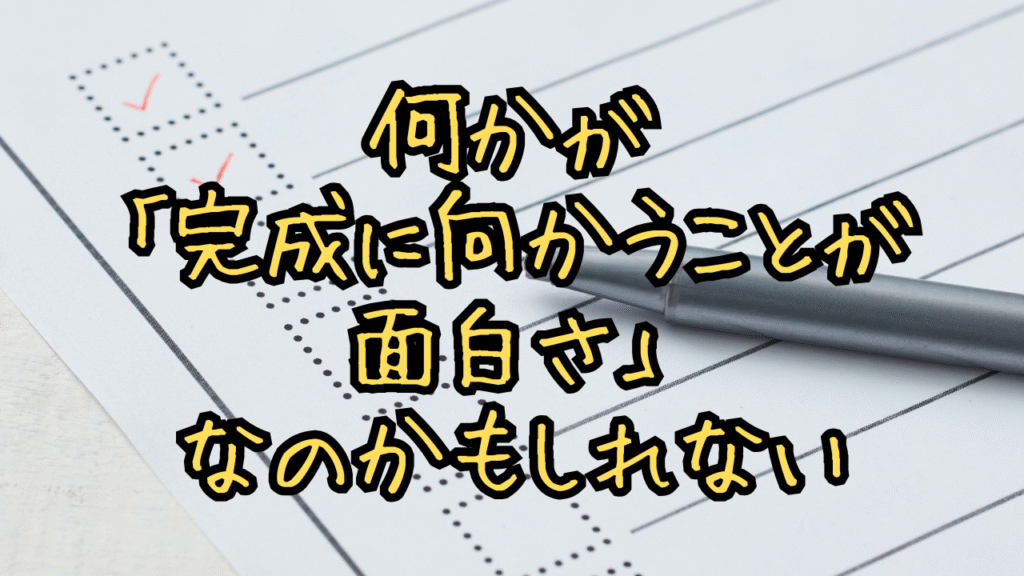
思ったことをつらつらと。
ゲームをしていて、ボードを埋めて強くなるの楽しい。
面白さもある。
それはボードを他の人よりも埋めることで優越感を得られるというのが根っこにある気がする。
自己満足的な側面もあるかもしれない。
また、何かが「完成に向かうことが面白さ」なのかもしれないとも思う。
ただ、完成した時点で、面白さはなくなる。
これはゲームをクリアした時に興味が下がるのもそうかもしれない。
楽しさでゲームを続けることはできるが、興味は下がるだろう。
また、ソシャゲなどはプレイヤーにずっと完成させないことが、面白さを生み出しているとも言える。
ただ、終わりが見えないというのは、かなりストレスではあり、どうやっても長期的に続けることができない。
結果として、ソシャゲは一定期間のサービス提供後終了してしまう。
いやいや、グラフィックとかどんどん進化していくから〜的な意見もあるだろう。
けれども、将棋や囲碁、シェスなど、ずっと遊ばれ続けているゲームもある。
50年後、今人気のソシャゲと将棋や囲碁、チェスのうち残っているのはどちらか?
誰しもが、将棋や囲碁、チェスだと答えるだろう。
しかしながら、将棋や囲碁、チェスも、膨大な棋譜があり、終わりが見えないと言えば見えない。
ソシャゲと将棋や囲碁、チェスの違いは何だろうか?
あくまで個人的な考えだが、将棋や囲碁、チェスは対戦によって結果がでることで、終わりがあることではないかと思う。
では、対戦格闘ゲームとの違いは何だろうか。
1回の対戦で終わりが定期的に訪れるため、長く続けられるのではないか?
しかし、現実には新しい格闘ゲームが出続けていて、古いものは遊ばれなくなる。
と思いきや、ストリートファイターというゲームにおいては、未だに過去のストリートファイターシリーズの大会が開かれていたりする。
他の格闘ゲームについても、長く遊ばれているものがいくつかある。
そう考えると、ゲームにおいて終わりがあることは、重要なのかもしれない。
ボードを埋めるというのも、終わりがある。
ボードが大きすぎて、一生かかっても埋まらないとしたら、それは終わりがないのと一緒。
つまり、ある程度終わりが見えていないとダメな気もする。
終わりというよりも、ゴールと言った方が良いかもしれない。
完成することもゴールだ。
つまり、ゴールがあることが、面白さの要素の1つと考えられる。
そして、そのゴールに向かって進んでいるとき、人は面白さを感じるということ。
だから、ゴールに向かって進んでいるかどうかがわからなると、面白くなくなる。
ゴールの設定はやはり大切なのだろう。
もちろん、ゴールがなくても面白さは発生する。
しかし、ゴールが無いと、永遠とエネルギーを注がなくてはならず、それが疲弊になる。
ゴールがあれば、一区切りとなり、休憩ができる。
ああ、そうか、休憩することが、何かを長続きさせる理由の1つなのは誰しもが知っている。
この休憩によって、一旦リセットされることが、継続していく上で大切な要素と言えそうだ。
ゴールに到達すれば休憩でき、そこでリセットされて、再び進むことができる。
休憩がなければ、いつか倒れてしまう。
そういうことなのだろう。
ふと、Todoリストが頭をよぎる。
Todoリストも似た側面があるのではないか。
最初は、Todoリストをチェックする、または線を引いていき、Todoを消化していくのが結構楽しい。
しかし、その作業は永遠と続く。
それが作業感を生んでしまうということだ。
定期的にTodoリストをリセットするタイミングが必要なのではないか?
そうか、棚卸しというのは、本来そうあるべきなのだろう。
一旦まっさらにする。
一旦ゴールする。
リセットする。
そして新たに始める。
儀式的なことでも意味があるだろうか。
これはTodoリストの考え方に新たな視点というか、Todoリストの方向性に影響を与えそうな気がする。
