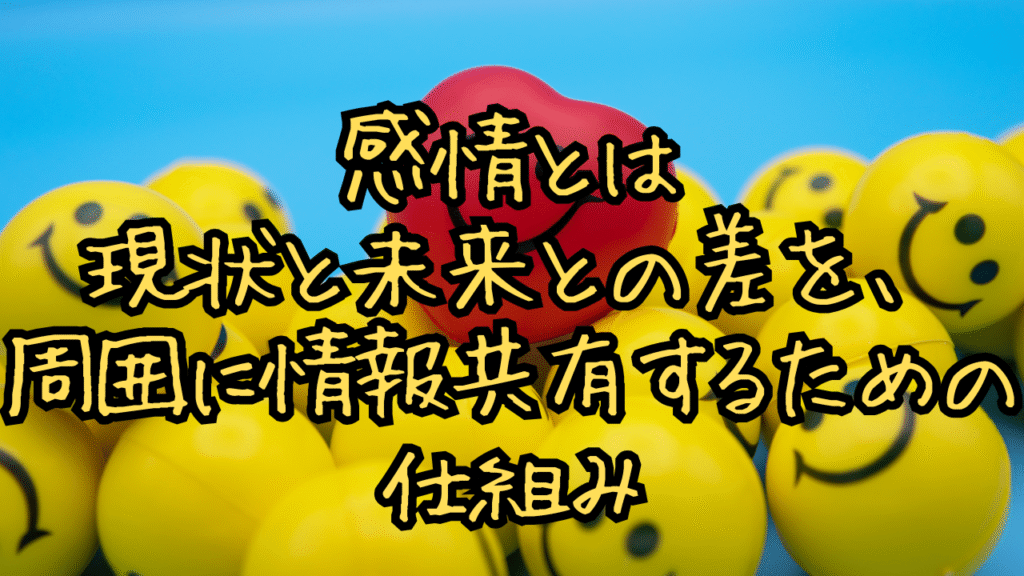
思ったことをつらつらと。
人は無意識に未来の状態と現在の状態を比較している?
人間というのは、未来の状態と現在の状態を比較し、未来の状態に近づける行為を行う生き物ではないか?
その未来がマイナスだから、その未来を実現しようとする?
または、その差を埋めようとする?
悲しい気持ちというのは、未来に得るはずだったメリットを失ったことから。
メリットにはいくつか種類があるように思う。
生命に関わることか、そうでないかが一つの基準か。
不安は長く続くもの、恐怖は一瞬のもの
例えば死。死への不安というのは、長く続くもので、ずっと考えてしまう状態。時間が長い。
しかし、死への恐怖というのは、短いもので、恐怖が長く続くことはない。
楽しいと快感の差も同じように感じる。
つまり、未来にどれだけそのメリット、デメリットが維持されるのか?によって、感情が発生してるということ。
ドラッグなどは快感をサクッと得られることがメリットと思われがちだが、未来に対してプラスであると感じることがいわゆる常習性を生んでいるようにも思える。
どういうことかというと、ドラックに依存する状態というのは、少し先の未来しか脳が認識できていないということだ。
その後に訪れるデメリットについては、考えられない状態といえる。
タバコも似たような面がある。
ただ、タバコはデメリットがドラッグよりも先の未来であり、そのためにドラッグよりもデメリットが見えにくいというのがあろう。
また、ドラッグにしてもタバコにしても短期的にはプラスの面があることは確かだ。
将来のデメリットを上回るメリットであれば、あえてドラッグやタバコをやるのは意味がある。
人間らしさ
わかり易い例が、余命が短い人だ。
極端な例だが、あと1日しか生きられないとしたら、ドラッグをやるデメリットはほぼ無い。
ドラッグというとマイナスのイメージがあるかもしれない。
例えば、病気で日々苦痛に見舞われているとしよう。
その人にモルヒネなどを注射することは、悪だろうか?
残りの1日の段階でもモルヒネは打つべきではないのだろうか?
当然、本人が望んでいなければ、打つべきではないが、本人が望んでいるのなら、それはプラスのことではないだろうか。
死ぬ前に酒を呑みたい、タバコを吸いたいという願い。
それを叶えることで余命が1時間短くなったとしよう。
それは悪なのだろうか。
やりたいことを我慢して1時間長く生きることに意味はあるのだろうか?
人間らしさというのは、やはり時間という概念と大きく結びついている気がしている。
感情とは現状と未来との差を、周囲に情報共有するための仕組み
人間は未来を見通せるからこそ人間なのだ。
そして、現在とのギャップが生まれることで、人は感情を発露させる。
感情とは現状と未来との差を、周囲に情報共有するための仕組みと考えることもできそうだ。
いささか極端かもしれないが、鳥が捕食者に狙われそうになって鳴き声で周囲に危険を知らせるのと、それほど差はないのではないか?ということ。
うつ病とは、悲しみが薄れるとは
うつ病とは、気分が落ち込むことではなく、未来を感じることができなくなり、未来と現在とのギャップが生じないことで、感情が発露しないからでは無いだろうか。
悲しみが薄れていくのは、時間が経過したからではなく、時間経過とともに残りの人生で悲しみむ時間が減るからではないか?
忘れるというのは、そもそも人間が未来を見て生きる生物だからとも言えそうだ。
未来と現在のギャップが感情で、感情が人間そのもので、感情は情報共有伝達ツールの1つであるという話。
