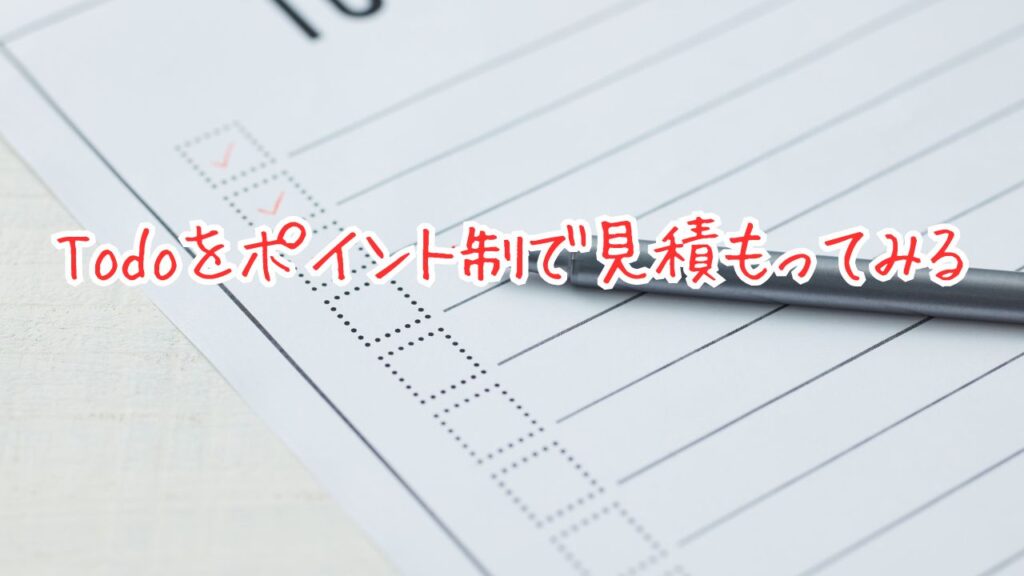
書き殴った文章をAIに整理してもらった。
目次
ポイント制による作業見積もりの提案
1. 作業量をポイントで管理する考え方
作業や仕事の見積もりを「時間」ではなく「ポイント(pt)」で表すことで、柔軟なリソース管理を行う。
- 例:
- 作業A:30pt
- 作業B:16pt
- 作業C:60pt
- 月のリソース:500pt などと設定し、数値化された目標を立てる。
時間で厳密に管理すると窮屈になりがちなため、バッファ(余裕)を含んだ「ポイント制」を導入するのが目的。
2. 週単位での試算
月単位だと概算が面倒なため、週単位での試算を実施。
1pt ≒ 30分 として計算。
実際の作業見積もり例
| 作業 | 時間換算 | ポイント |
|---|---|---|
| A | 1日30分 ×数日 | 7pt |
| B | 1時間半 | 3pt |
| C | – | 21pt |
| D | 4時間 | 8pt |
| E | – | 16pt |
| F | 6時間 | 12pt |
| G | – | 10pt |
| H | – | 4pt |
| 合計 | – | 112pt |
3. 労働時間との比較と負荷の確認
1日8時間労働の場合、
- 8時間 × 5日 = 40時間
- 40時間 ÷ 0.5時間(=1pt)= 80pt
つまり、実際の見積もり(112pt)は週の想定リソース(80pt)を超過しており、オーバーワーク気味であることがわかる。
4. 精度よりも振り返りのためのツールとして
このポイント制は、厳密なスケジュール管理というよりも、
- 自分の作業量を客観的に振り返る
- タスクの負荷を可視化する
といった目的に向いている。
目安として活用し、大幅に超える場合はタスク削減を検討する。
5. 休息と非生産時間の重要性
「何もしていない時間」や「ぼんやりしている時間」も重要であり、
それを完全に排除して効率だけを追うのは望ましくない。
どの程度まで厳密にポイント化するかも、バランスを取る必要がある。
6. 週末・イベントの扱い
週末(土日)の使い方も全体リソースに影響する。
イベント参加などを詰め込みすぎると、
- 当日の時間だけでなく
- 回復・休息にかかる時間
も含めてリソースを圧迫するため、週末の活動も考慮に入れたポイント設計が求められる。
まとめ
- 時間ではなくポイントで作業量を見積もることで柔軟な管理が可能。
- 実際に試算すると、現状のタスク量がリソースを超過していることが可視化された。
- 精密な管理よりも、自分の負荷感を把握し、改善に繋げるツールとして有効。
- 休息や週末の活動も含めたトータルバランスを意識することが重要。
以下、AIにまとめて貰う前の原文
仕事や作業の見積もりを数字で出して、そのリソースの中で毎月の目標を設定するのはどうか?
例えば、
- 作業Aは30pt
- 作業Bは16pt
- 作業Cは60pt
みたいな。
で、月のリソースを500ptみたいに決める。
作業時間でかっちり決めてしまうと、窮屈な気がするため、ポイントにするという感じ。
つまり、バッファや余裕が必要じゃないかということ。
それも含めてptにする。
月だと概算がめんどくさそうだったので、週単位でやってみた。
作業時間の概算を1ptあたり30分ぐらいに考えてみる。
実際に今やっている作業を概算してみた。
- 作業Aは1日30分換算 7pt
- 作業Bは1時間半換算 3pt
- 作業Cは 21pt
- 作業Dは4時間 8pt
- 作業Eは 16pt
- 作業Fは6時間 12pt
- 作業Gは 10pt
- 作業Hは 4pt
合計は、112pt
1日8時間労働換算だとすると、16×5=80pt。
ということで、5日作業だと溢れている。
つまり、結構キツいということ。
また、何もしてない時間とか、ぼんやりしている時間とかも大切な気がするし、どの程度まで厳密にやるかもポイントか。
単純に自分の作業の振り返りをするのには、良いかもしれないし、作業量の目安にはなりそうな気がする。
大幅に越えるようであれば、タスクを減らすしか無い。
あと、土日をどうするか?
明らかに土日にイベント参加を詰め込むと、その後の休む時間も含めて、大きく時間を取られている。
そういうのをどこまで考慮するか?
そのあたりも、考慮しないといけない気もする。
