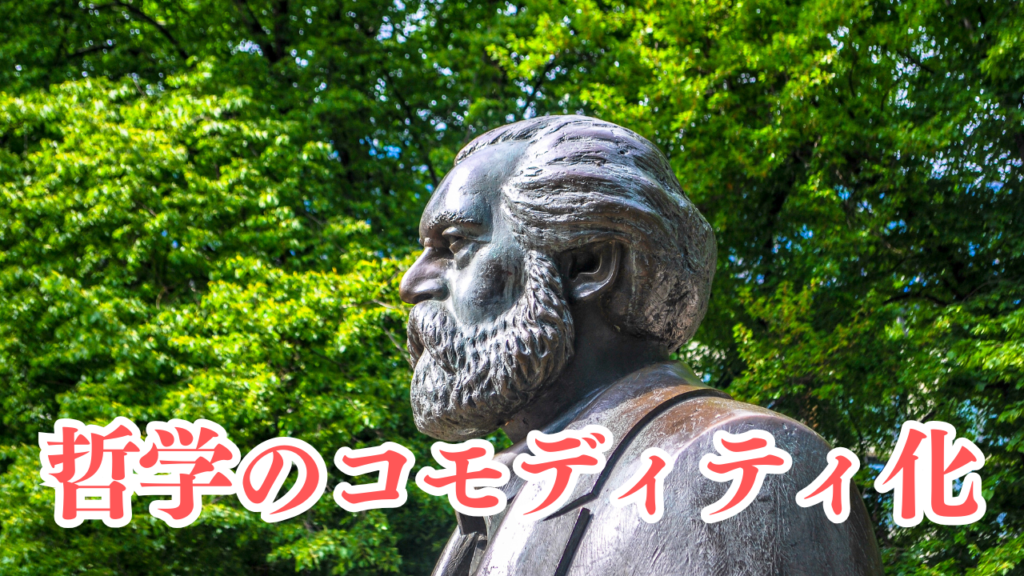
個人的に思ったことをつらつらと。
目次
科学によって哲学は居場所を失いつつある
最近哲学についていろいろと考えています。
哲学というと、過去の偉人たちが真理、本質を探る学問で、何か難しいというイメージが強いかなと。
なので、好きな人は好きだけど、敷居が高かったり、難しいことが理解できないと、哲学ってやっちゃダメな感じを思っている人も多いのではないでしょうか。
ただ、現在の哲学は行き詰まりをみせています。
その最大の理由は、科学の発展です。
これまで多くの偉人たちが思考をめぐらせ、世界について考えてきましたが、科学によって世界がどんどん解明されていくに従って、偉人たちの考えが間違っていたことが判明しています。
じゃあ、偉人たちは本当にダメだったのか?というと、そういうわけではありません。
哲学者たちによって生み出されたものもたくさんあるからです。
しかし、もはや世界は科学者たちの独壇場になっており、哲学者が考えることが減ってきているというのが現状と言えるでしょう。
哲学に残されている道は、人の心、精神的なものしかないと、個人的に考えています。
しかし、心や精神というのも、心理学や脳科学などによって、どんどんと解明されているのが実情です。
心や精神について、すべての解明がされるのはまだ先ですが、逆に言えば、解明されると哲学という分野は、ほぼ終わりを向かえるのかなとも思っています。
その時、本当に哲学は死んでしまうのかもしれません。
果たしてそうなのか?
個人的にですが、哲学の最終領域は、人生、生き方、価値観なのではないかな?と思っています。
何を大切にするのか?どう生きるのか?は自分で決める
どれほど、心や精神、脳の解明が進んだとしても、科学が発展したとしても、人生において、「何を大切にするのか?」や「どう生きるのか?」というのは、残り続けるからです。
例えば、小説家になりたいと思ったとしましょう。
しかし、AIなどの発達によって、テストを行い、小説家としての才能は低いと判断されたとします。
論理的には小説家を目指すのは、正しい行動ではありません。
けれど、それでも小説家を目指す選択ができるのが、人間の生き方なのではないでしょうか。
一生貧乏かもしれない、そもそも小説家にすらなれないかもしれません。
ただ、その道を選ぶことが自分でできることが、人間としての尊厳というか、人間らしさなのかなと。
様々な選択肢がある中で、どの道を選ぶのか?
それを考えるのが、哲学なのではないだろうか?ということです。
また、価値観で言えば、例えば「家族を大切にするのか?」「友人を大切にするのか?」「自分を大切にするのか?」というのもあります。
これって人によって違いますよね。
育ってきた環境やそれまでの人との出会い、読んだ本、得た情報によっても変わっていくと思います。
そして、そこに正解はないわけです。
それこそが哲学に残された道なのではないかなと。
人生の答えは求めるものじゃない、自分で出すものだ
哲学とは自分で考えることが重要だと思っています。
というか、そもそも哲学とは、個人の心の叫びみたいなものだと自分は認識していて、主観の強いものかなと。
客観的な話は、科学に任せてしまえばよいのです。
もちろん、科学的な話も重要。
何かを考える上で、科学の情報も含めた上で、自分の人生、生き方、価値観を考える、決めるということです。
大切なのは、自分で考えること。
誰かの話を聞いて、本を読んで、動画を見て、答えを見つけるものではないと個人的には思っています。
「人生の答えは求めるものじゃない、自分で出すものだ」ということです。
次の時代は哲学のコモディティ化
前述したように、哲学においては自分で考えることが重要だと思っています。
しかし、自分で考えることって、実は当たり前のことなんじゃないかなって。
正直言えば、昔は大手メディアの力で、多くの国民がその情報に流されていました。
ところが、インターネットの発達によって、大手メディアのウソや間違いが明らかになり、大手メディアの信頼は失墜していると言えるでしょう。
もちろん、すべての情報が間違いとは言いませんが、昔に比べれば、信頼度は圧倒的に低くなりました。
さらに、近年では昔の悪事が暴かれることも多いです。
その影響で、職を失ったり、会社が危機的状況になったりしていますよね。
多くの人たちがSNSで声をあげ、それが社会を動かすこともあります。
しかし、SNSにはデマも非常に多いです。
例えば、草津温泉の草津レイプ虚偽事件は本当に酷いものでした。
間違った情報を拡散し、草津温泉の信頼は失われ、虚偽だったことがわかった後も、その信頼は昔ほどに回復しきれてはいないでしょう。
なぜ、このようなことが起きてしまったのでしょうか?
あくまで個人的にですが、デマを流した人たちというのは、自身で考えることをしていなかったのではないか?と思っています。
誰々が発言した内容だから間違いない、どこどこのメディアで発信された内容だから信頼できるなどという理由で、発信してしまったのかなと。
これは、昔の大手メディアを信頼しきっていた大衆の時代と変わりません。
そうならないためには、どうするべきなのか?
自分で考えるしかないと思っています。個々人が自分で考え、判断するしかないということです。
それが今後、さらに求められていくと個人的には考えています。
そして、自分で考えるということは、まさに哲学なわけです。
それが哲学のコモディティ化だと思っています。
つまり、「哲学のコモディティ化とは、個々人が自分で考え、自分で答えを出すこと」です。
哲学対話は哲学のコモディティ化の一端
その時に、過去の偉人たちがどういう思考で結論を導き出したのか?というのは非常に参考になるかなと。
考えるとはどういうことなのか?ということを考えるのも哲学ですね。
ただ、いきなりそんな難しい話をされても・・・と思います。
個人的にも、難しい話をくどくどとしても仕方がないのかなって。
で、自分で考えることのきっかけとして、個人的には哲学対話が良いと最近は思っています。
哲学対話とは、テーマに沿って個々人が自分の意見を言う場です。
ざっくりと紹介動画を作成しました。
哲学対話は答えを出す場ではありません。ですので、議論はしません。
あくまで自分の考えを深める場。
自分の経験に基づいて話すことが前提なので、過去の哲学者が〜〜というのは無し。
まさに、人生、生き方、価値観について考える場であり、哲学のコモディティ化の端緒ではないかなと。
他にもそういった自分で考える場やツールなどがあって、今後はそれらが重要になってくると考えています。
余談:大切なのは考えることを放棄しない
デマに流されないためには自分で考える必要があると書きました。
しかし、完璧な人間はいないですし、著名な人でもデマを信じてしまうことがあります。
大切なのは、デマを信じてしまった時に、考えることを放棄しないことかなと。
間違いを認め、なぜ信じてしまったのかを考えることが重要ということです。
ただ、被害者ヅラして、考えることを放棄してしまうと、また同じ間違いをしてしまうでしょう。
それでは、昔と一緒です。
考え続けること、それがもしかすると、哲学の本質なのかもしれないなとも思いました。
