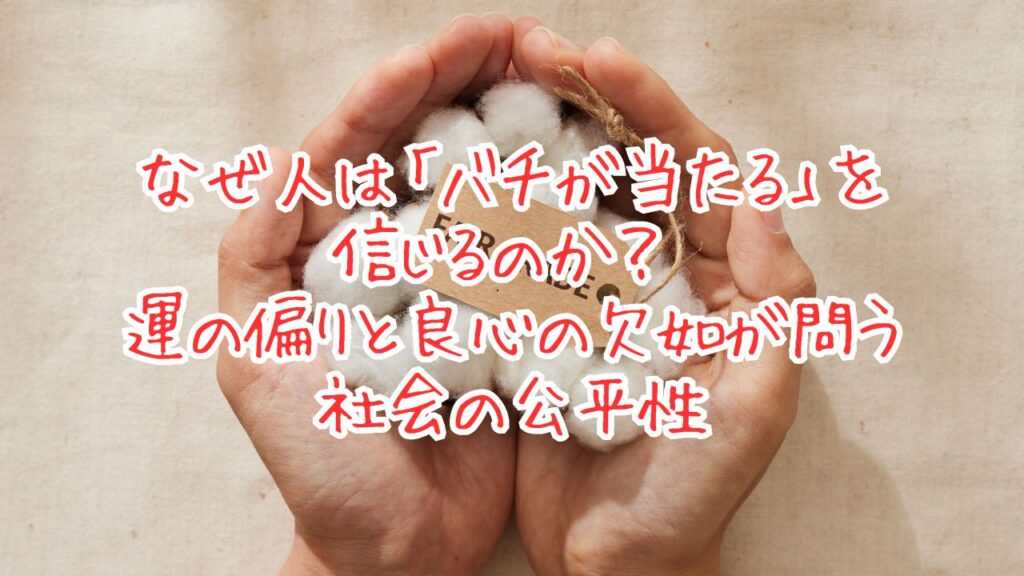
書き殴った文章をAIに整理してもらった。
目次
🧐 迷信「悪いことをするとバチが当たる」を信じる理由と社会のブレーキ
このセクションでは、「悪いことをするとバチが当たる」という迷信がなぜ信じられるのか、その背景にある道徳や倫理の役割、そして現代社会におけるその変化について考察します。
1. 迷信を信じる心理的な背景
- 教育の影響: 小さい頃からの道徳的な教育が、悪い行為への抑止力として大きく影響していると考えられます。
- 社会秩序の維持: 協調や協力といった社会的な概念を理解した上での行動を促すための規範として機能しています。
- 運の概念: 「運は皆に巡ってくる」という考えと同様に、悪い行いに対して公平に罰が下るという期待感が背景にある可能性があります。
2. 「運」と「罰」の数学的・現実的な偏り
- 逆正弦定理: 数学的には、低い確率の事象が連続して発生する偏りがあることが指摘され、これは運の偏り(例:サイコロで1が出続ける)を示唆しています。無限に続ければ平等になるが、現実世界では偏りが生じます。
- 現実の不平等:
- 親ガチャ: 生まれた環境(親の経済力など)が人生に大きな偏りを与える最も分かりやすい例です。
- 罰の偏り: 悪いことをしても、捕まる人と捕まらない人がおり、成功する人もいれば失敗する人もいます。罰が当たらない人も存在するのが現実です。
3. 良心の欠如と社会的な不利益
- 良心を持たない人々: サイコパスやソシオパスなど、良心や罪の意識を持たない人々は、悪いことの認識がないため、心が傷みません。
- 正直者が損をする構造: こうした人々が多く存在する場合、普通に悪いことをしない人たちが損をする事例が多々発生します。
4. 悪いことをしない合理的な理由と道徳の役割
- 法律による抑止力: 現代社会では、国家と法律が存在するため、法律違反をすれば罰を受けるという合理的な理由が悪い行為をしない主な動機です。逃亡生活は窮屈であり、非合理的です。
- 道徳・倫理の役割: 人間は合理的な生き物ではないため、法律があっても罪を犯します。道徳や倫理、そして「バチが当たる」という迷信は、この非合理的な行動を少しでも減らすブレーキとしての役割を果たしています。
⚖️ 文明の発展と失われゆくブレーキの再構築
文明の発展に伴い、従来の道徳的ブレーキが弱まる中で、それに代わる新たな規範の必要性と、社会の平等性についての提言をまとめます。
1. 法律以外のブレーキの消失
- 宗教・迷信の崩壊: 文明の発展と価値観の多様化により、宗教的な教えや「バチが当たる」といった迷信が信じてもらえなくなりつつあります。
- 求められる代替手段: 法律以外のブレーキの役割を果たしていたものが失われつつあり、それに代わる新たな規範、つまり道徳や倫理の再構築が求められています。
2. 規範の法律化と壁としてのマナー
- 権利の人工性: 人権などの「権利」は、真理として存在するものではなく、人間が考えたものであり、あるという前提で話が進んでいます。
- 道徳・倫理の法律化: この考えに基づけば、道徳や倫理についても、法律のような形で規制することが一つの解決策として考えられます。
- マナー・礼節の課題: マナーや礼節は「目に見えない壁」であり、特定の地域におけるルールとして機能しますが、知る機会がないことが問題です。これらを学校教育で教えるべきかという提言があります。
3. 平等への提言と課題
- 運のルール化: 「運」についても、平等という観点でルール化することが提案されています。
- 教育格差: 機会の平等は法律化されているものの、「親ガチャ」や教育の機会の不平等(塾通いによる学力格差)は未だ解決されていません。
- 子どもへの選択権:
- 子どもには、生まれる場所や社会を選択する権利がありません。
- もしかすると、子どもが自分が生きたい社会を選択できるようなシステムこそが、真の平等かもしれません(ただし、子どもの判断能力という課題があります)。
- 自己選択のコスト: 自分の社会に適用できない場合、異なる社会へ移行するシステムは存在するものの、移住コスト(費用、言語、仕事)が高すぎるため、多くの人は実行しません。このハードルを下げることで、人が社会を選べる世界になる可能性があります。
🇯🇵 日本社会の現状と変化の展望
現在の日本社会に対する評価と、社会を変えていく上での視点についてまとめます。
1. テクノロジーと生活の選択
- テクノロジーの忌避感: テクノロジーに追われる生活を嫌がる人もいますが、多くの人は、田舎での自給自足のような生活を選ばず、テクノロジーによって豊かになった生活を手放したくないと考えています。
- 日本の住みやすさ: この事実は、現在の日本が全体としてかなり過ごしやすい、生きやすい社会であることの裏返しとも言えます(生きづらさがないわけではないが)。
2. 社会変革と過渡期の課題
- 漸進的な変化: 社会は少しずつしか変わることができず、ドラスティックな変革は困難です。
- 犠牲を払う人々: 今、生きづらさを感じている人々は、社会が変化する過渡期において、ある意味犠牲を払っている状態にあります。
- 日本の良い面: 変革は必要であるものの、過渡期においては、日本の社会の良い面にも目を向けるべきではないか、という考えが示されています。
以下、AIにまとめて貰う前の原文
悪いことをするとバチが当たるというのは迷信だが、なぜそれを信じようと思うのか?
社会の秩序的な話、協調、協力という概念を理解した上での行動であるならば、わからなくもないが、そこまで考えて行動している人も少ないだろう。
小さい頃から、そういった教育をされてきていることの影響は大きいと思う。
実際、文化圏の違いによって、価値観は異なる。
同じようなことに、運もある気がしている。
運は皆に巡ってくるみたいな。
でも、実際には、そういうことはない。
数学的には、逆正弦定理というのがあって、低い確率が連続して起きることがある。
例えば、サイコロを振って、1が出続ける人もいるという話。
もちろん、ずっと続けていけば、すべての目が同じように出るのだけれど、そのずっとってのは、無限に近くて、それはリアルではない。
つまり、運に偏りがあるということだ。
まあ、親ガチャとかが、一番わかりやすい例なのかもしれない。
親が金持ちだから幸せな人生を送れるかどうかは別で、あくまで運に偏りがあるという話の例。
全体で見ると、結構平等だけれど、どうやっても偏りってのは出てしまう。
すべて平等というわけにはいかない。
悪いことにしてもそうで、悪いことをしても捕まる人もいれば、捕まらない人もいる。
それで成功する人もいれば、失敗する人もいる。
罰が当たらない人もいるということだ。
悪いことをすると心が〜という意見もある。
しかし、世の中には、サイコパスやソシオパスといった、良心を持たない人たちも存在する。
彼らにしてみれば、悪いことという認識がない。
罪の意識はない。
だから、心が傷まない。
そういう人たちが多くいると、普通に悪いことをしない人たちが、損をする。
そのような事例は枚挙にいとまがない。
では、悪いことをした方が良いのだろうか?
現状では、多くの人が国家に属し、その社会の中で生きている。
そこには法律が存在する。
よって法律違反をすれば、捕まって、罰を受けることになる。
逃げ延びることもできるかもしれないが、ずっと逃亡し続ける生活は、とても窮屈だろう。
これが、合理的に考える悪いことをしない理由。
しかし、人間は合理的な生き物ではなくて、わかっていても罪を犯す。
それを少しでも減らす役割、ブレーキとしての役割が、道徳とか倫理で、悪いことをしたら罰が当たるという迷信も、含まれるのだろうなと。
ところが、文明が発展し、宗教などが崩壊していく中で、当然、悪いことをしたら罰が当たるというのも迷信になって、信じてもらえなくなりつつある気がしている。
つまり、何が言いたいのかというと、法律以外のブレーキ的な役割を果たしているものが、無くなってきているのではないかという話。
そして、それに代わる何かが今求められているのではないかということ。
道徳とか倫理がずっと言われ続けているのは、そういう理由なのだと思う。
ただ、例えば、様々な権利について、そもそも人間が考えたものであって、権利なんて存在はしていなかった。
人権っていうのは、人間が考えたものと言う話。
そこに真理的なものは、存在せず、あるという前提で話が進んでいるというか。
だから、法律で縛るわけなのだが。
そうなると、道徳や倫理についても、法律のような形で規制するのが、良いのかもしれないとも思う。
先日、マナーというテーマで哲学対話をしたときに思ったのだけれど、マナーって目に見えない壁みたいな感じだなと。
礼節とかもそう。
壁はあるんだけど、知らないというか。
法律は国で規定されているけれど、マナーとか礼節って、特定の地域におけるルール。
法律ほどの拘束力はないけれど、破ると厄介なことになるという感じ。
もちろんマナーについても礼節についても、どこかには文章として明文化されている。
しかし、それを知る機会がない。
それが現状、問題なのではないかなとか。
問題とまではいかないか。
ただ、そういうマナーとか礼節についても、学校で教えるのが良いような気もしている。
一方で、そういう道徳や倫理やマナーや礼節などで、雁字搦めになってしまうと、生きるのが窮屈になるような気もする。
そのバランスが重要なのだろう。
と、話が少しそれてしまった。
言いたかったことは、道徳や倫理などについても法律化した方が良いのではないか?ということ。
また、運などについても、平等という観点でルール化するのはどうか?とも思う。
もちろん、今だって機会の平等は法律化されている。
ただ、親ガチャについては、まだ法律化されていない。
教育の機会の平等もそう。
義務教育はあるけれど、お金持ちの子どもは、塾に通うことができて、そこに学力格差が生まれているのは、誰しもが知っていることだ。
そして、日本においては、未だに学歴社会が残っている。
そのため、学力格差が、その後の人生に与える影響は大きい。
それらを是正するような平等な社会は、果たして築けるのだろうか?
完璧な平等は無理だったとしても、今よりは少しだけ子どもたちにとって平等な社会を作れないだろうか?とも思う。
当然、我が子可愛さというのはあるから、他の人の子どもなんてどうだって良いと思う人も多かろう。
また、自分自身のことを考えてみても、なかなか自分の人生に手一杯で、他の人のことを考える余裕はない。
そういう意味では、多くの人がそうなのかもしれないし、そうであるならば、人は平等を求めていないのかもしれない。
それはそれで、アリな考え方のようにも思える。
全員が納得すれば、不平等社会だって問題はない。
ただ、思うのは、そこに生まれてくる子どもには選択権はないんだよなあということ。
それは、全員に言えることかなとも。
日本に生まれ、日本で育ったことで、日本の文化という価値観を強制されているのでは?という話。
もし、違う国に生まれていれば、まったく違う価値観を持っただろう。
そう考えていくと、子どもが自分が生きたい社会を選択できるような社会が、もしかすると平等なのかもしれない。
ただ、子どもの頃に、どれだけ判断ができるのか?という課題もある。
なんとも難しい話だ。
もしかすると、社会に自分が適用できないのであれば、違う社会に移行できるようなシステムがあると、それらの問題は解決できるかもしれない。
当然、今の社会だって、それはできる。
けれど、多くの人はそれをしない。
その理由は、コストだろうなと。
他の国に住むには、移住の費用もかかるし、言葉も勉強しないといけないし、移住先で働き口を探したりと、結構ハードルが高い。
そのハードルを下げることができれば、人が社会を選べる世界になるかもなと。
また、選択肢が少ないというのも、現状の課題かもしれない。
以前に、テクノロジーは人を豊かにするか?という哲学対話に参加した時に、多くの人がテクノロジーに対する忌避感を持っていた。
パソコンとか、スマホとか、SNSとか、テクノロジーによって生み出されたものに追われ、新しいことを学び続けないと、社会で生きていけない。
あとは、AIが怖いとか。
で、自分が思ったのは、そういうものをすべて捨てて、移住すれば良いじゃんって。
田舎に行って、自給自足の生活をすれば良いじゃんって。
でも、多くの人は、それを嫌がる。
ハードルが下がったら移住するかというと、たぶん移住しないだろう。
結局、テクノロジーによって豊かになった生活を手放したくないのだ。
そう考えていくと、今の日本というのは、かなり過ごしやすい、生きやすい社会なのだろうなとも思う。
もちろん、生きづらさが無いとは言わない。
自分も、メンタルブレイクをして、3年ぐらい何もしていなかった時期がある。
ただ、全体で見た時に、日本はそこまで悪くないんじゃないかとも思える。
少しずつ変えていくしかなくて、少しずつしか変われなくて、今、生きづらさを感じている人は、その間にいて、ある意味、犠牲を払っている状態ではある。
それに甘んじろとは言わないけれど、もっと日本の社会の良い面を見ても良いのかなとは思ったりする。
変えていくことはマストだけれど、過渡期だから、ドラスティックに変えることはできないから。
そんなことをぼんやりと思った。
