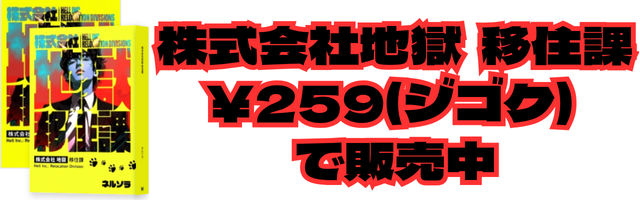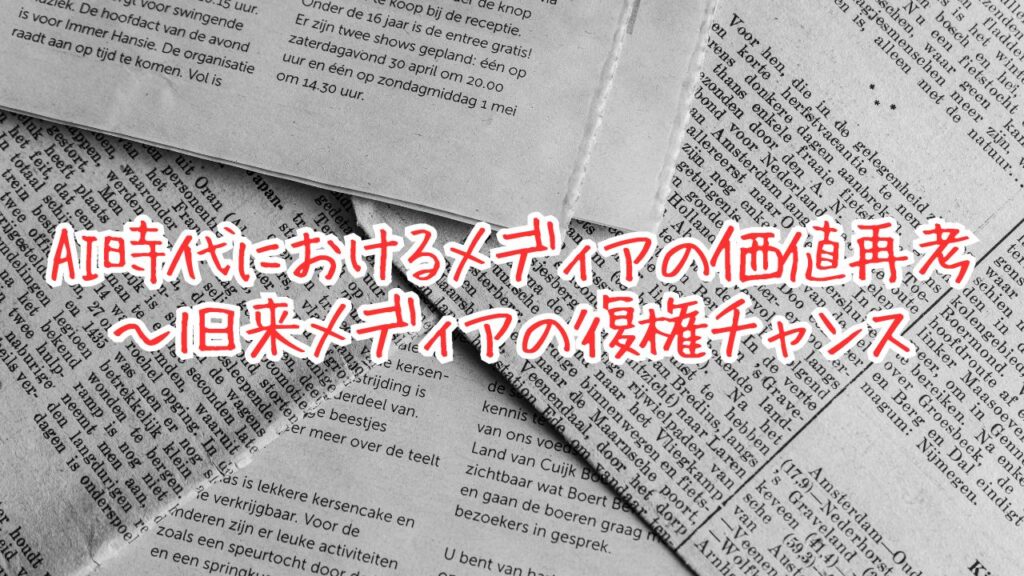
書き殴った文章をAIに整理してもらった。結構良い感じな気がする。
目次
AIの進化とフェイクコンテンツの拡大
近年、AIの進化は著しい。
テキスト、画像、動画いずれの分野でも、誰でも容易に高品質なコンテンツを生成できるようになった。
その一方で、フェイクニュースやフェイク動画の増加が顕著であり、今後も爆発的に増えることが予想される。
このような状況だからこそ、一次情報を扱う新聞やテレビの価値が再評価される可能性がある。
AIの本質的な弱点:一次情報の欠如
AIの最大の弱点は、AI自身が一次情報を持たない点にある。
AIは既存コンテンツを学習し、それを要約・最適化して出力するにすぎない。
学習データや検索情報が制限されれば、AIは「過去のまとめ」しか提示できなくなる。
これは、既存メディアがAIに対して情報ブロックを行うということだ。
しかし、情報をAIに提供しないことは、AIユーザ=未来の読者を失うことにつながる。
AI時代のマーケティング:学習される側になる重要性
今後、人々はAIを通じて情報を得て、購買や行動の判断を下すようになる。
AIが学習していない情報は、人々の目に触れることすらない。
したがって、企業やメディアは、自らの情報をAIに学習させ、AIの出力に反映させる戦略を取る必要がある。
これを拒否することは、市場を自ら狭める行為であり、特に人口減少が進む日本においては致命的と考える。
新聞・テレビの最大の強み:一次情報の保有
新聞やテレビが持つ最大の強みは、一次情報の収集力である。
個人では難しい取材を、メディアの「ネームバリュー」により容易に行える。
この強みを活かし、正確な一次情報を提供するメディアとしての価値を高めることが重要だ。
現状の課題:調査報道・信頼性・リアルタイム性の低下
AI(Gemini)も指摘するように、新聞・テレビの価値は本来、
- 調査報道の深さ
- 信頼性の高さ
- リアルタイム性
にある。
しかし、現在の新聞・テレビはそれらの多くを失っている。
インターネット上では情報が即座に拡散・消費され、偏向報道や誤報が露呈し、リアルタイム性でもネットに敗北しているのが現実だ。
一次情報の信頼性を高める施策
今後は、フェイク情報の氾濫に対抗するため、一次情報の信頼性を最大化する必要がある。
そのための施策としては、
- 専門分野(特に理系)にプロフェッショナルを配置
- ソースや修正履歴を明示
- 情報の理解度を高める努力
が考えられる。
これらにより、「正確性=ブランド価値」を確立する。
ビジネスモデルの転換とアライアンス構想
短期的対策
AI学習を特定ベンダーと契約し、ライセンス収入を得ることは即効性がある。
長期的戦略
しかし、単独契約は敵を作るリスクがあり、
新聞社間のアライアンス形成が理想的だ。
さらに、他メディアとも連携することで交渉力を高められる。
アーカイブの活用
- 過去記事のアーカイブを全面解放
- 誤報は修正し、修正履歴を公開
これにより、透明性と信頼性が向上する。
新たなメディアモデル:新聞版「TVer」の可能性
テレビ業界の成功例として「TVer」がある。
TVerはアクセス数・滞在時間ともに世界上位であり、動画アーカイブによる滞在価値を高めている。
新聞社も同様に、
- 過去記事の有料アーカイブ
- 時系列でのニュース閲覧機能
- 新聞社横断の検索システム
などを実装すれば、新しい形の価値あるニュースプラットフォームを築ける可能性がある。
コンテンツ戦略:質で勝負する時代へ
センセーショナルな見出し競争は、ネットの情報量には勝てない。
新聞・テレビは、正確で一次的な情報の質に特化すべきだ。
人々がネット上の情報を見た際、「最終確認は新聞社のソースを見よう」と思わせるブランド価値を築くことが復権の鍵である。
AIの活用と収益モデル
新聞社やテレビ局の膨大なアーカイブを基に、専用AIを開発するのも有力な手だ。
一次情報に基づくAIは、他の生成AIにはできない強みを持つ。
収益化の方向性としては、
- サブスクリプションモデル(定額課金)
- 情報利用の認証マーク制度
- 専用検索AIの利用権
が考えられる。
これにより、一次情報の信頼性 × 継続的収益を両立できる。
結論:新聞・テレビ復権への道
新聞・テレビには、依然として豊富な資産と取材ネットワークがある。
しかし、ネットのやり方を真似しても勝てない。
AI時代においては、
- コンテンツの量ではなく質
- 二次情報ではなく一次情報
が勝負の分かれ目となる。
AIが進化した今こそ、一次情報の価値を最大化し、メディアの信頼を再構築する好機である。
以下、AIにまとめて貰う前の原文
最近、AIの進化が目覚ましい。
テキストもそうだし、画像や動画もそうだ。
クオリティについては、まだまだ人間に余地が残されているものの、誰でも簡単にそれなりのコンテンツを生成できるようになったことは間違いない。
その結果、フェイクニュースやフェイク動画が増えてきた。
これから、その数は圧倒的に増えていくだろう。
だからこそ、逆に、新聞やテレビの価値が上がっていく可能性がある。
現在のAIには弱点がある。
それは、AI自身が一次情報ではないという点だ。
AIは、必ず学習という工程を経る。
その学習には、既存のコンテンツが使われる。
最近では検索した情報を出してくれるようになったが、結局はAI自身が一次情報ではないということだ。
現状のAIはどこまでいってもまとめでしかなく、最適化でしかない。
もし、一次情報をAIが学習できなくなったり、検索できなかったり、表示することを制限されたら、AIは過去の情報のまとめしかできなくなる。
つまり、既存メディアによる情報ブロックだ。
しかし、これはあまり有益ではないだろう。
というのも、SEOからAIOに突入かで書いたように、今後、多くの人がAIの出力によって物事を選択するようになる。
そのときに、AIに情報が学習されていなければ、出力されることはない。
例えば、美味しいパン屋を教えてくださいとAIに依頼したときに、AIが学習していない情報はどうやっても出てこない。
つまり、AIに頼っている人間には、情報が届かないのだ。
AIにいかに学習してもらい、AIの出力に自分たちの情報を出してもらうかが、今後、マーケティングで求められるとも言える。
よって、AIに自分たちのコンテンツを学習させない、表示させないというのは、AIユーザを切り捨てることになり、結果、市場が狭くなる。
今後、日本においては人口減少が確定しており、さらに市場が小さくなれば、もはや生き残るのは難しいだろう。
ここで改めて、新聞、テレビの強みについて振り返ってみると、やはり新聞、テレビの強みは一次情報であるという点だ。
個人的には、これが新聞、テレビの最大の強みであり、そこを主眼におくべきだと思っている。
ちなみに、この件について、Geminiに聞いたところ、
- 調査報道の価値
- 信頼性の高さ
- リアルタイム性
について挙げていた。
それが普通の回答だろう。
そして、残念ながら、そのどれもが、今の新聞、テレビには欠けている。
結果、このままいけば、確実に凋落していくのは間違いない。
なぜなら、それらの情報は、あっという間にネットで拡散され、そして消費されていくものばかりだからだ。
調査能力はある程度あるのかもしれないが、インターネットの住人たちの数にはかなわない。
信頼性なんて、偏向報道しかり、誤報しかり、そしてそれをインターネットの住人たちに暴かれてきた。
リアルタイム性など、もはや新聞、テレビでは勝てない。
それらはすべてインターネットの強みなのだ。
そこで、新聞やテレビが戦っても、どうやっても勝てない。勝てるわけがない。
だからこその一次情報の強みを活かすのだ。
新聞やテレビは、これまである程度の地位を確立してきた。
言ってしまえば、ネームバリュー的なものである。
個人が取材を依頼するよりも、新聞やテレビが依頼した方が、取材を受けてくれることが圧倒的に多いだろう。
そこが新聞、テレビの強みなのだ。
それを強化し、それを売る。
今後、フェイクニュースやフェイク動画がどんどん増えていき、インターネットはさらに真実を見極めるのが難しくなるだろう。
だからこそ、一次情報の信頼性を高める必要がある。
それには、情報の理解度の高さ、ソースの表示など、様々な施策が必要だ。
特に情報の理解度については、新聞、テレビが圧倒的に低い。
特に理系分野についての内容は、恐ろしく稚拙だ。
それらの分野に、プロフェッショナルを入れるのが、最初に行うべきことだろう。
ビジネスモデルの転換も必要だ。
とりあえずは、AI学習許可を特定のAIサービスベンダーと結ぶのがすぐに金になる。
ただ、長期的に見た場合、それが本当にメリットを生むかどうかは、微妙なところだろう。
というのも、単体で契約すると逆に敵を生み出す可能性があるからだ。
やるべきは、新聞社のアライアンスである。
理想的には、他のメディアも組むべき。
そうすれば、ある程度、契約を有利に進めることができるだろう。
また、新聞社については、過去のアーカイブをすべて解放するのが望ましい。
誤報があれば、修正し、それをちゃんと告知する。
理想的には修正箇所がわかる方が良い。
そうすることで信頼性が高まる。
さらに言えば、あくまで個人的に思っているのだが、新聞社が合同の組織を作り、1つのメディアを作るというのも手だ。
いわゆるTVer。
TVerについては、一時期オワコンなどと言っている方もいたが、世界でトップ100以内のアクセスを誇り、さらに動画というコンテンツによって滞在時間も長く、かなり強いサイトと言える。
惜しむらくは、単純に、マネタイズがうまくいっていないというだけ。
個人的には、過去の放送について、アーカイブを見れるようにして、それを有料課金にすればよいのでは?と思っている。
いわゆる、サブスクリプションモデルだ。
テレビの録画が必要無くなる世界への突入である。
それと同じことを、新聞社もできるのではないか?と思っている。
各新聞社は、独自の色を出しやすいものだけをメインに取材すれば良い。
基本的にどの新聞社であっても変わらないもの、例えば、交通事故などは、合同の会社が取材し、すべての新聞社に配る。
共同ニュース通信と似たような形とも言えるだろう。
あと、個人的に同じニュースについては、時系列で見れるような仕組みもあれば、新聞に価値が出ると思う。
そして、各新聞社を横断的に見ることができれば、新聞社の色が出やすくなるし、様々な視点を獲得できるだろう。
これらは、一次情報だからできることだと思う。
また、センセーショナルな見出し合戦には意味がない。
そんなものは、圧倒的に数が多い、インターネットの住民たちによって駆逐されていく。
いくら頑張っても無理だ。
だからこそ、一次情報として、正確性を最大まで高めることに注力する。
多くの人がネットを介して情報を見たときに、新聞社にソースを確認しにいくという認識ができれば、新聞社が復権できる可能性が高い。
それはテレビも同様だ。
AIの活用はどうか?
個人的にだが、過去の新聞社やテレビのデータアーカイブを利用して、専用のAIを作るというのもアリな気がしている。
これも一次情報だからこそできる強みだと言える。
余計な情報を廃して、事実、エビデンスを重視することで、新聞やテレビの情報を調べずには、物事が語れないという状態にできれば、その地位は復権できるだろう。
収益については、やはり、サブスクリプション一択。
いかに、ユーザにサブスクリプションを契約してもらうかが、最大の課題。
方向性として、新聞社の情報を利用するには、認証マークが必要で、それを使用するにはサブスクリプションが必要というのが一つ。
前述したようなアーカイブや新聞専用の情報検索AIなどの利用というのもある。
と、勢いで書いてみたけれど、少なくとも、新聞やテレビというのは、これまでの遺産があり、ツテもあり、それをフル活用すれば、まだまだ可能性のあるメディアであるということが書きたかったのだ。
インターネットに引っ張られていては、たぶん、復権は無理だ。
これまで新聞やテレビはインターネットを馬鹿にしてきたが、結局、今はインターネットのやり方を真似、そして、その土俵で戦おうとしてる。
それが土台無理な話なのだ。
AIの進化によって、それが確定的になった。
もはや、コンテンツの量では勝てない。
だから、コンテンツの質で勝負する必要がある。
そして、現状のAIでは難しい一次情報こそが、最大の強みなのだ。
そこに活路があると、個人的には思っている。