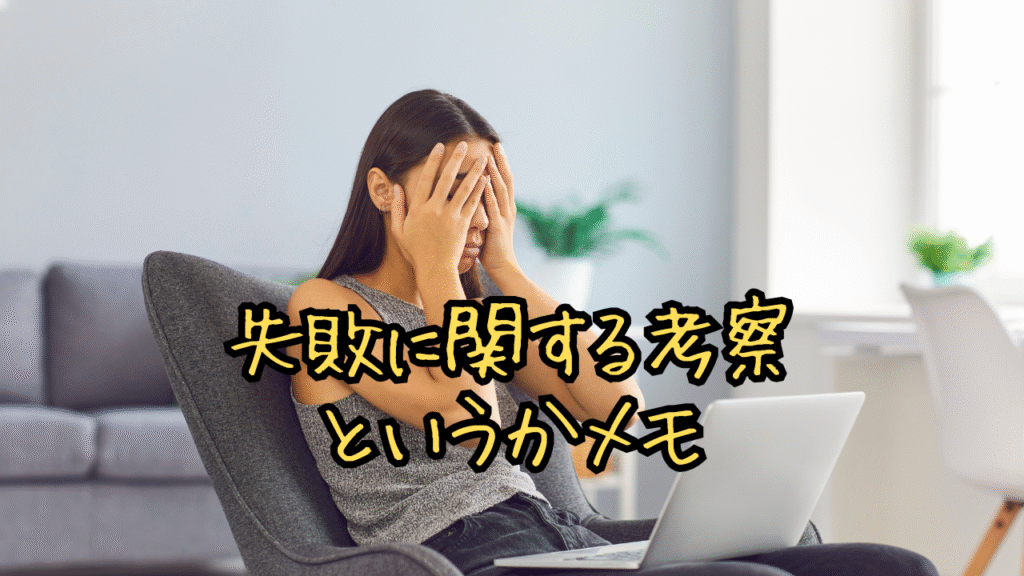
たぶん、失敗の科学を読んだときのメモ的な何か。そもそも失敗というものは存在するのだろうか?的な話。
ざっくり要約
この文章では、「失敗とは何か」という問いに対し、辞書的な定義から始まり、データベースの不在、失敗の種類、原因、そして失敗に対する考え方まで多角的に考察しています。
まず、失敗は「不利益を被ったこと」や「目的を誤り良い結果が得られないこと」と定義されます。失敗に関する包括的なデータベースは見当たらず、大きな事件に関するものはサービス停止していることが示唆されています。
失敗の種類は、「織り込み済み」「結果としての失敗」「回避可能であった失敗」の3つに分類されます。
失敗の原因は多岐にわたり、「未知」「無知」「不注意」「誤判断」「手順の不遵守」「調査検討の不足」「制約条件または環境条件の変化」「企画不良」「価値観不良」「組織運営不良」の10個が挙げられています。
失敗に対する考え方として、失敗の原因は人間にあるという視点や、自然界における失敗の意味合い、社会の成熟による失敗の捉え方の変化が述べられています。DNAの存続を生命の意義とするならば、現代社会における失敗は必ずしも失敗とは言えない可能性も示唆されています。
失敗の責任追求は、デメリット回避や自己保身が理由として挙げられています。しかし、最終的な目的達成の過程であれば失敗は問題ないという考え方や、「失敗は成功の母」という言葉も紹介されています。科学の進歩においては、多くの失敗が後の研究者の無駄を省き、新たな知見につながるという側面も強調されています。
つまり、失敗は単なる否定的な結果ではなく、捉え方や文脈によって意味合いが異なり、学びや進歩の糧となる可能性を秘めていると言えるでしょう。
失敗とは何か
ある事象に対して不利益を被ったこと
[名](スル)物事をやりそこなうこと。方法や目的を誤って良い結果が得られないこと。しくじること。「彼を起用したのは―だった」「入学試験に―する」「―作」
失敗(しっぱい)の意味 – goo国語辞書
失敗についてのデータベースは無さそう。
大きな事件の失敗についてはあるけど、サービスは停止。
頓挫したと思われる。
参考 → 失敗知識データベース
失敗の種類は、大きく次の3つに分けられる
失敗学 – Wikipedia
- 織り込み済みの失敗。 ある程度の損害やデメリットは承知の上での失敗。
- 結果としての失敗。 果敢なトライアルの結果としての失敗。
- 回避可能であった失敗。 ヒューマンエラーでの失敗。
失敗の原因
失敗に対する考え方
失敗の原因は人にある。というか、失敗という認識自体人間が作り出した概念とも言える。
自然界において失敗は即死を意味することも多く、そもそも論として生物のあり方というか、存在意義がDNAの存続であるならば、個体の失敗はあまり意味がない。
なぜなら他の個体が残っていれば特に問題がないからだ。
また、生き残った個体、言うなれば成功した個体が生き残っていくという自然淘汰の考え方にも合致する。
つまり失敗しても問題ないというか、そもそも失敗するかどうかは不明で、多様な個体を出すことで失敗しても問題ないようにしているわけである。
しかし、人間においては社会の成熟によって失敗=死ということがなくなり、失敗してもやり直すことが可能になった。
いわゆるセーフティネットなどがその一例である。その結果、失敗というものがクローズアップされるようになったわけである。
前述したようにDNAの存続が生命の意義であるならば、いわゆる現代社会における失敗というのはそもそも失敗ではないとも言える。
なぜ失敗の責任を追求するのか?
そもそも人は失敗するものである。失敗が一度も無い人間は存在しないと言えるだろう。
ただ、失敗をどう捉えるかによって失敗ではないという考え方もできるが、ここでは失敗の定義として目的を達せられないという意味で考えると、誰しもが自身の目的を達せられなかった経験があると思う。
そこに異議を唱えるものはいないと思う。
さて、ではなぜ人は失敗の責任を追求するのか?
失敗することで被るデメリットを回避したいから、自身の失敗を認めたくないし、他者に失敗の原因を求めることで自身は安全圏にいることができるから。
他にも理由はありそうだ。
失敗の原因10個
- 未知
- 無知
- 不注意
- 誤判断
- 手順の不遵守
- 調査検討の不足
- 制約条件または環境条件の変化
- 企画不良
- 価値観不良
- 組織運営不良
失敗は個人の主観?
そもそも失敗したとしても最終的な目的を達成する過程であれば、問題ないとも言える。
失敗は成功の母という言葉もある。
近年の科学では、もはや驚嘆すべき新発見というのが難しい。
また、ぶっちゃけて言えば多くの科学者が実験をし、失敗というか、求めた結果が得られなかったことで、可能性を潰し、それを共有することで、後の科学者が同じことをしなくても良くなる。
つまり無駄なことを省けるわけ。
また、過去の実験で条件が足りなかったりしたことに気づけば、それを新たに実験すれば良いだけの話。
そしてそれもまた知見となる。
全く同じ実験だったとしても、それにも意味はある。
結果が同じということは、論理が正しいということでもあるし、世界の環境が変化していないという裏返しでもある。