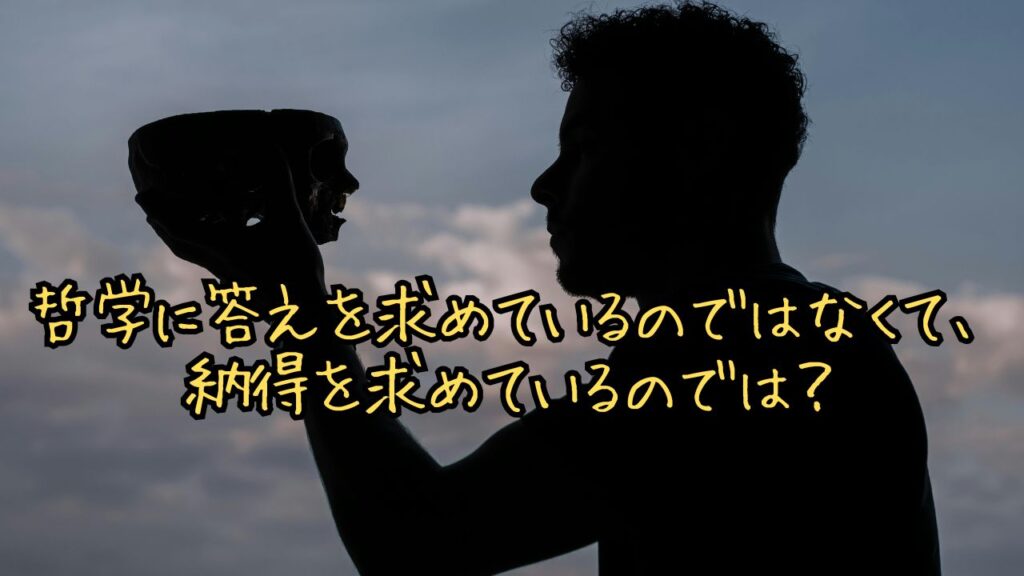
そんなことを、ふと思った。
科学の場合は、明確な答えというものがある。
なぜなら、世界の法則は、変わることはないからだ。
過去の科学が書き換えられるのは、観測のズレや間違い、または新しい法則の発見、法則の破れなどの発見などによって起きる。
それは、正しい答え、または正しい答えへ繋がる道なのだ。
しかし、哲学は違う。
哲学に明確な答えというものは存在しない。
極論を言えば、人それぞれなのだ。
真理ではなく、個人個人の答え、つまり、それが納得ではないかという話。
哲学はその昔、真理を求める学問だった。
しかし、その役目は、科学が担うことになる。
真理とは何か?
個人的には、ざっくり言い換えれば、共通の理みたいな感じ。
これは、再現性を基本とする科学そのものとも言えるかもしれない。
では、哲学は共通の理を見つけたのか?
考え方のアプローチ方法については、様々生み出してきた気がするが、共通の理のようなものは、生み出せていない気がしている。
もし、これは哲学が生み出した共通の理というのがあれば、ぜひ知りたいところ。
共通の理というからには、証明と再現性を必要とする。
誰が提言し、誰が証明し、誰が再現性を担保したのか、合わせて知りたいなと。
で、話を戻すと、個人的にそのような共通の理が哲学には存在しないのではないかなと思っている。
あくまで、ある人の考え方でしかないというか。
例えば、幸福とは何か?という問いに対して、哲学は明確な答えがあるだろうか?
科学的なアプローチについて考えるとすれば、ドーパミンなどの脳内物質の放出量、時間などを指標にし、幸福を定義できるかもしれない。
しかし、哲学では、そのような定義ができない。
じゃあ、哲学に意味はないのか?というと、そういうわけではないと個人的には思っている。
幸福とは何か?という問いに対して、答えは人それぞれなのだ。
で、それを考えることが、哲学なんだと思う。
そして、考えた結果、自分が納得できれば、それがその人の答えなのだ。
それが人類の共通の理である必要はない。
つまり、「哲学に答えを求めているのではなくて、納得を求めているのでは?」ということに繋がる。
それが、哲学の本質なのではないかなと。
そう考えると、誰々がAと言ったから、答えはAだというのは哲学では成り立たたない。
あくまで、自分はAと考えるのが哲学なのではないか?という話になる。
その自分の答えを、考え続けることが哲学ではないだろうか。
最近、哲学対話という会に参加している。
それは、自分の考えを深めるため。
何か、共通の理を求めているわけではない。
だから、哲学対話で、答えがAだと決めつけるような発言は、なんとなく違和感を覚える。
特に、誰々が、ある本には、Aと書かれていて、それが答えだと言われると、ちょっと辟易すらする。
なぜなら、哲学とは考え続けることだと思っているから。
誰かの考えを答えとしてしまうと、その時点で考えることを止めてしまっているのと同義だ。
どんなに偉い哲学者の言葉であっても、それを疑うことが、大切なんじゃないだろうか。
ちなみに、科学は、現在観測できていることから、再現性が確認できたものを法則としているが、新しい観測データがでてきて、その法則に破れが見つかったら、サクッと考え方を変える。
あくまで、今の法則は暫定的なものとしてしか考えていない。
個人的には、哲学についても同様だと思っていて、環境が変わったり、時代が変化していくことで、Aだと思っていたことが、変わっていくことが往々にしてあると思っている。
そういうことからも、誰かの言葉や考えを鵜呑みにするというのは、哲学ではなくて、考えることをしないAIと変わらないんじゃないかなって。
どうなんでしょうね。
