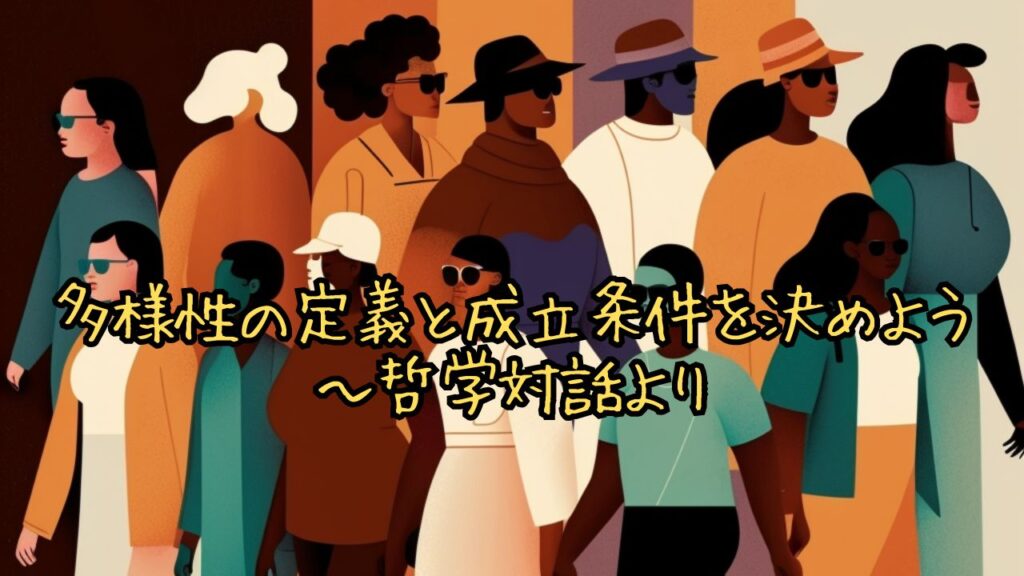
先日参加した哲学対話で感じたことをつらつらと。
テーマは多様性。
多様性という言葉を使い分ける人たち
まず最初に対話していて感じたのは、多様性という言葉を使わけている人が結構いるなという印象。
具体的には、内向きと外向きで。
内向きというのは、端的に言えば、味方である人々、外向きというのは、逆に敵である人々のこと。
味方というのは、仲間だったり組織だったりグループだったり。
敵というのは、わかりやすくいえば論敵、やり込めたい人たち。
どのような使い分けをしているかというと、味方については「ゆるい多様性」を適用し、自分たちは多様性を担保できているという感じ。
敵については、「厳密な多様性」を適用し、相手が間違っている論拠とする感じ。
言ってしまえば、論破したい、または自分の正しさを証明したい的な。
いろいろな議論動画を見ていると、そんな風に個人的には感じました。
なぜ、そのように感じたかと言うと、多様性の定義が曖昧だからです。
もっと言うと、多様性が成立する条件が明確でないと感じています。
多様性の定義
今、社会的に使われている多様性という言葉は、多様な人種、ジェンダーを受け入れる的な感じで使われることが多いと思います。
多様性を主張することは、人種やジェンダーで差別をしないという主張の裏返しなのかなと。
これが「ゆるい多様性」です。
で、「厳密な多様性」になると、多様性の効果が加わってくる感じ。
それがごっちゃに使われているように感じていて、議論が噛み合っていないのだろうなと。
というのも、「ゆるい多様性」については、誰も反対はしないと思うからです。
そこに、「多様性には効果がある」みたいな話が加わってくると、話がおかしくなってくる印象。
つまり、多様性って差別せず受け入れることが目的だったはずなのに、良い効果があるから多様性を重視すべきだみたいに話がすり替わっているんですよね。
そこで齟齬が生じてしまう。
なので、まずは多様性の定義を共有する必要があるんだろうなと。
また、その定義については、その場、時代などで変化しそうな気がするので、多様性を担保したいのであれば、都度都度、多様性の定義について、参加者で対話し、共通認識を持っておく必要があるように思いました。
多様性が成立する条件
もう1つ、多様性の議論で話して置く必要があるのが、多様性が成立する条件です。
これは多様性、多様性と言っている人に、ちゃんと聞いてみたいなと。
個人的に、今、多様性と言っている人たちにおける多様性って、人種やジェンダーの多様性のように思っています。
けれど、それで本当に多様性が成立しているのでしょうか?
具体的に言えば、宗教、イデオロギー、スキル、知識、国や出身などなど、人間にはさまざまな要素があります。
例えば、移民問題を考えるとしましょう。
人種とジェンダーの多様性を確保すれば、良い対話ができるでしょうか?
全員、特定の宗教を信奉していたら、特定の宗教を排除するようなことが起きないでしょうか?
他にも、飛行機のエンジンを作る際に、さまざまなジャンルのエンジニアは必要ないのでしょうか?
新しい、ジャンボジェットのエンジンを作ろうというプロジェクトにおいて、特定の飛行機のエンジンを作る専門家だけを集めた場合、多様性が成立しているのでしょうか?
どちらも、人種とジェンダーの多様性を確保はしたとしても、おそらく偏った方向に進むことは、誰しも容易に想像できるのはないでしょうか。
こんな当たり前のことが、多様性という議論においては、置き去りにされている気がします。
つまり、多様性が成立する条件が、曖昧なのです。
この曖昧さを利用して、いかにも多様性がある方が良いというのは、根拠薄弱な気がします。
何にしても目的を達成することが重要では?
次に、ジェンダーの多様性について考えてみましょう。
例えば、同性愛者同士をマッチングするインターネットのサービスがあったとしましょう。
そのサービスを利用する人たちは、同性愛者ばかりです。
多様性は成立しないと言えるでしょう。
果たしてこのサービスは問題なのでしょうか?
多くの人が問題ではないと思うでしょう。
なぜなら、同性愛者のマッチングが目的だからです。
つまり、大切なのは、目的を達成することであって、多様性ではないのです。
目的を達成するのに、多様性が必要であるときに、多様性について考えれば良いと自分は考えています。
その時に、前述したように、まず多様性の定義をし、多様性の成立条件を明確にしておく必要があるでしょう。
その多様性は、あくまで目的を達成するために必要なものなので、一般的な多様性とは異なる定義、条件で構わないと思っています。
例えば、新しい飛行機のエンジンを作るにあたって、別なジャンルのエンジニアや科学者を加えたいなどです。
この場合の多様性は、経験や知識の多様性ということになるのかなと思います。
そこに、人種やジェンダーは必要ありません。
大切なのは、経験と知識ですから。
むしろ、そのような人材を集める際に、人種やジェンダーにこだわらないことが多様性なのではないかとも思います。
そもそも多様性がある
人種、ジェンダーにこだわらないのであれば、日本人だけランダムに抽出したとしても、多様性があるといえるでしょう。
人は皆、それぞれ違います。
むしろ、それを人種という括りで一緒くたにしてしまうことの方が、多様性という意味から考えると、逆に良くないのではないでしょうか?
ジェンダーについても、マイノリティの方たちだって、それぞれ違います。
皆が同じジェンダーではないのです。
LGBTQの方を1人チームに入れたから多様性みたいに言うのは、やはり違うのではないでしょうか。
女性的な男性もいますし、男性的な女性もいます。
それを男性、女性で区切ることが本当に正しいのでしょうか?
個人的に感じたのは、結局、多様性という言葉を使って、相手を論破したいだけなんじゃないかって。
自分たちの正しさを証明したいだけなんじゃないかって、そんな風に思ってしまいます。
本気で多様性を考えるなら
本気で多様性を考えるとしたら、どうやって多様性を成立させたら良いのかなと。
個人的に思ったのは、脳の分類。
まあ、脳については、まだまだ未知というか、生きている人間の脳をハックするのにもう少し時間がかかるので、当面無理かもしれません。
ただ、脳をマッピングして、ある程度、距離がある人たちをランダム抽出すれば、真の多様性が実現できそうな気もします。
けれど、多様性を実現できたとして、一体、何をするのだろう?というのが個人的な考えです。
多様性を作ることが目的なので、その時点で、目的は達成されているため、それ以上、先が無い気がします。
結局、厳密な多様性なんて実現はできないですし、実現する意味もないのかなと。
人種やジェンダー、もちろん宗教やイデオロギー、知識やスキル、国や出身などで差別しない、受け入れること、平等に扱うという「ゆるい多様性」ってのが、社会における多様性なのではないでしょうか。
