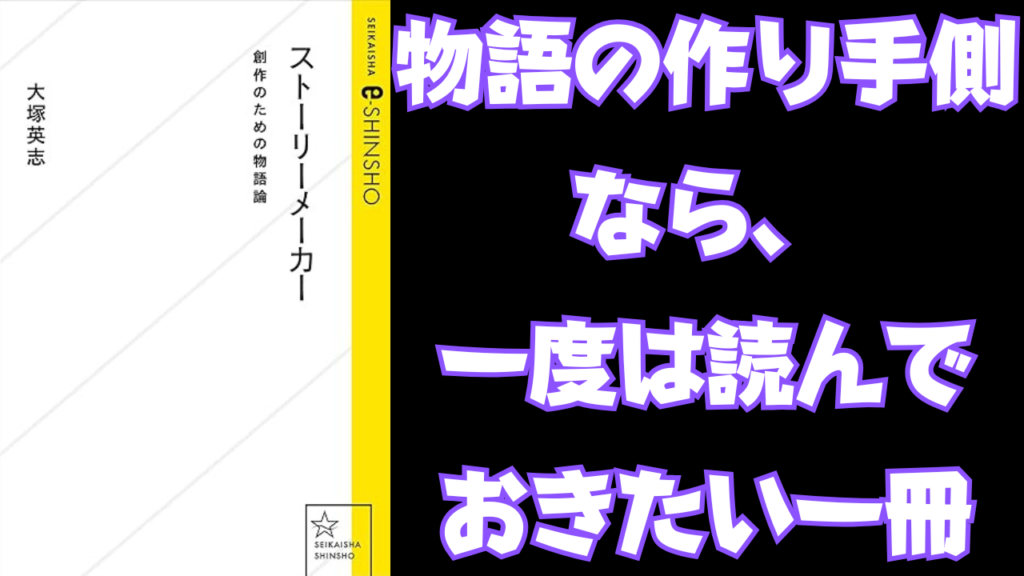
評価・レビュー
☆5/5
物語を構造で分解し、物語の基本を作るための本。
序盤は、物語がどんな構造でできているのかを、海外の研究や作品をベースに解説しています。
で、メインは終盤から。
カードでプロットを作る
まず、カードでプロットをつくる方法。
知恵や生命、信頼など様々な言葉が書かれたカードを裏向きにしてシャッフルし、所定の順番で並べていきます。
で、全部めくって、それを元にプロット(物語)を作っていくという方法です。
最初は主人公の現在からはじまり、結末までの全体的な流れが出来上がるというもの。
これは面白いなと思いました。
ストーリーが全然浮かばないのであれば、かなり便利に使えると思います。
全然関係無いですが、その昔、友人と物語を作るさいに、それぞれが2つのキーワードを書いて、それらのキーワードをすべて満たすような物語を作ってみるという試みをしたことあります。
ベタなキーワードもあれば、わけわからんキーワードもあって、そこから物語を考えるのは楽しかったです。
ちなみに、わけわからんキーワードを書いたのは自分。「目が見えない世界」という無茶苦茶なキーワードでした。
ただ、それをそのまま使うのではなくて、そのエッセンスを入れるということ、主人公の敵役が目が見えない仮面を被った男という設定で入れ込みました。
仮面はもちろんシャアをモチーフにしています。仮面を被っている理由も明確になり、それはそれで良かったなと。
物語を作るストーリーメーカー
30の質問に答えることで、物語のプロットが作れるというものです。
あくまでプロットで、物語に必要な要素を書いていく質問形式。
書く内容は、そこまで細かくする必要はなく、最初はサクサク埋めていく感じで進めると良さそうです。
物語曲線的な
次に、物語の全体像を曲線で描いたものに、それぞれ書いていきます。
そうすると、盛り上がりがどこで、どう進めるべきかが見えてくるというものです。
図示するのは非常に良いアイデアだなと個人的には思いました。
ストーリーメーカーは使えるか?
個人的には非常に使えると思いました。
ただ、あくまでこれは物語のベースとなる部分でしかなく、面白い物語が書けるかどうかはまた別の話。
少なくとも物語を物語るスタートラインに立てるという感じかなと思います。
なので、ストーリーメーカーを使うと使わないとでは、かなり違いがでるでしょう。
実際に、自分は今、小説を書いているのですが、すべての質問に答えることができました。
つまり、物語を物語る最低限の要素が揃っているということ。
逆に、ざっくりとメモだけした小説ネタは、全然質問を埋めることができなかったので、要素が足りてないことがわかりました。
ですので、小説を書く前に、一度ストーリーメーカーの質問に答えられるかどうかを試すだけでも、かなり違うと思います。
しかし、世の中の素晴らしい小説家の先生は、これを全部頭の中でやってしまうのですから、本当に凄いなと。
という感じで、本書は物語の作り手側なら、一度は読んでおきたい一冊だと思います。
以下は本書を引用しつつ、個人的なメモ。
物語の文法の基本は2つ
物語の文法の一番の基本は二つある、と考えて下さい。
一つは「欠落したものが回復する」というパターン。もう一つは「行って帰る」というパターンです。
これは、いろいろな物語を頭で考えてみると、どれもそうだなと思いました。
基本的に何か欠けているからこそ、主人公はそれを取り戻そうとするというのが、基本の基本なのかなと。
「行って帰る」についても本文で、子どもから大人への通過儀礼的な例の話が出てきますが、結局子どもも欠けている存在と言えます。
なので、主人公は基本「欠けている者」である必要があるというのが、今の自分の見解です。
この「欠けている」というのは、能力的なものの場合もありますが、人間の場合もあるかなと。
いわゆる、家族や恋人が亡くなることで、「欠けてしまった」となるわけです。
また、ほのぼの系は、何も欠けていないのでは?という疑問もあるかなと。
ただ、ほのぼの系って、結局ほのぼのしてしまう状態があるわけで、ほのぼのが無い状態、つまり「ほのぼのが欠けている状態」から始まっていると考えることもできます。
さらに、無敵キャラが主人公の場合、例えば、無敵すぎて、戦いがつまらない状態も欠けていると言えるでしょう。
また、主人公が何か求めている時点で、それは欠けている状態、欠けてしまった状態です。
これは主人公だけでなく、他の登場人物にも言えるかなと。
目的というのは、結局欠けているものを埋めるために設定され、そして登場人物たちは、その目的に向かって進むわけです。
結論として、あらゆる物語の登場人物たちは、「欠けているもの」を「取り戻す、埋める、生み出す」ために「目的」を作り、行動するという構造になっていると言えるかなと。
逆に言えば、欠けていない登場人物というのは、目的が無いため、行動することができず、物語が動かないと言えます。
境界線を越える
「行って帰る」物語にとってまず第一に重要なのは、この「境界線」を超えて「向こう側」に行くということです。
本書では、「行って帰る」という物語の基本構造について、かなり細かく書かれています。
で、この「行って帰る」が物語の基本構造だと言われると、多くの人が頭に描く物語があるでしょう。
今だと、異世界転生ものです。
異世界転生ものが作成しやすいのは、最初の段階で、「行って帰る」という物語の基本構造が用意されているため。
人気なのも同じ理由と言えるでしょう。
革命のファンファーレ 現代のお金と広告の中で、人はネタバレしたものしか買わないみたいな内容がありました。
異世界転生ものという時点で、物語の基本構造が出来上がっていることがわかっているため、ある意味、ネタバレした状態と言えます。
ネタバレという意味では、水戸黄門もそうですね。
基本的に毎回同じパターンです。
そう考えると、異世界転生ものというのは、ある意味、水戸黄門なんだなとも思いました。
まあ、時代劇と言った方が良いかもしれません。
と、他にも目からウロコが落ちるような話がいろいろとあって非常にためになりました。
