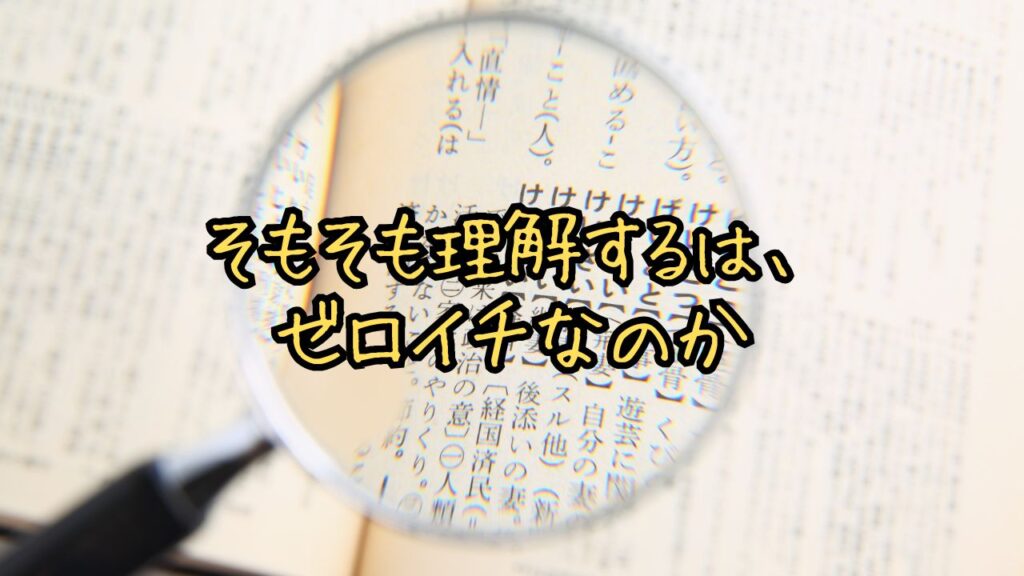
ふと、理解するって、ゼロイチなのかなって。
なんか、理解した!って言うと、100%わかったようなニュアンスがある気がする。
けれど、本当に100%理解することってあるのだろうか。
まあ、数式なんかは、そうかもしれないな。
ただ、数式は記号としての共通認識というか、ルールの記憶的な側面もあるかもしれない。
なんとも言えないけれど。
と、何が言いたいかというと、理解はゼロイチじゃなくてグラデーションじゃないかって話。
人の話を聞いて、100%理解することは無理だと思う。
であれば、理解度が0〜99%という感じで、グラデーションになっているんじゃないかなって。
いやいや、ちゃんと理解しているよって意見もあるのもわかる。
前述の数式の例はそんな気がする。
ただ、例えば「右に曲がって」と言われた時に、右に曲がったとして、その曲がる角度、スピードは、「右に曲がって」と言った人のイメージとぴったり合うのかというと、違うのではないか、ということ。
結局、目的がある程度達成されていれば、小さな違いというか、差異は気にしないようにできているような気がする。
その違いをどこまで許容できるかは、人によって違うのだろう。
つまり、ちゃんと理解していなくても、目的が達成できれば、社会通念上問題ない、理解していると認識される、という感じ。
でも、本当は、そこにグラデーションがあるんだろうなと。
だから、理解したというのは、目的を達成できる情報を得たと解釈することができそうな気もした。
その目的は、前述の「右に曲がって」のようなものもあれば、親密度を上げるとか、いろいろとある気もする。
数式についても、人によって理解度は違う気がする。
例えば、もっとも美しい数式の1つ
e=mc^2
についても、人によって感じ方が違う。
エネルギーは質量x光速度の二乗に値し、質量とエネルギーが変換できるとか、世界はデジタルであるとか、そういう話。
で、目的もその都度変わる。
単純に雑学的な情報共有というのであれば、もっとも簡単な数式の意味を理解していれば、理解したと認識されるだろう。
しかし、この方程式から、さらに自分の意見を述べ、議論をするのであれば、世界はデジタルであるとか、そういった話になってきて、単純な意味の理解では、理解しているとは言えない気もする。
そう考えれば、理解するとは、やはり目的が達成できる情報を得たという解釈は合っているかもしれない。
この目的達成という観点では、ゼロイチが成り立つ気がする。
つまり、目的達成ができれば100%理解しているということ。
目的達成ができなければ、理解していないということ。
わかりやすい判別方法な気もする。
理解度にそれぞれ違いがあったとしても、目的達成にフォーカスすれば、理解するということを捉えやすいかもしれない。
まあ、テストなどが理解度の確認として使われるのも、そういうことなのだろう。
ただ、テストだって100点じゃないと合格というわけではない。
やはり理解度に違いがある。
けれど、60点などの目標があり、それを越えていれば、合格、つまり理解している認識される。
合格、不合格という点で見れば、ゼロイチだ。
で、そのようなことを意識すると、理解に対する考え方が変わる気がする。
つまり、目的を達成できるかどうかで、自分が理解をしたかどうかを判定するということだ。
情報として、知識として、脳にインプットされたことが理解ではなく、得られた情報によって目的を達成できるかどうかが大切ということ。
目的達成のためには行動が必要で、行動できないということは、やはり理解していないということにもなりそうだ。
知行合一に近い考え方かもしれない。
