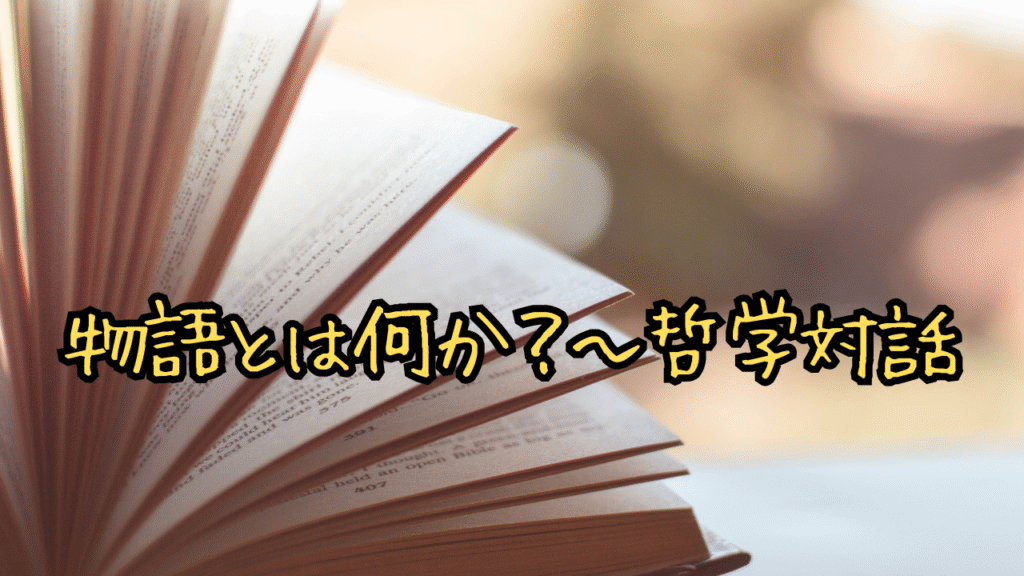
onecafe 学生哲学カフェの哲学対話に参加してきました。
テーマは「物語とは何か?」です。
初めての参加でしたが、楽しく話すことができました。
終わった後にご飯会があったのですが、残念ながら予定があって、帰ることに。次回は行きたい。
で、本題。
今と昔で物語の役割が異なる
今と昔では物語の役割が異なるという話がでてきました。
昔は経典的なものとか、寓話的なものが物語で、それは共同体、社会を維持する役割として使われたのかなと。
で、今の物語については、エンタメがメインということです。
話も今の物語についての話が中心になりました。
物語の消費
私たちは物語を消費しているのでは?という話がでてきました。
余ったリソースを使う、エネルギーを使う、退屈をどうにかするために、物語を読むという考えです。
物語については、文章だけでなく、映画やドラマ、アニメなんかも含みます。エンタメなので。
消費にも良い面と悪い面があるのでは?という話がでてきて、そういう考え方もあるなあと。
個人的には、悪い面だと思っても、後から良くなることもあるというスタンス。
例えば、今のeスポーツなんかはそうですよね。
昔なら、ゲームは遊びで無駄だと考えている人がいた気がしますが、プロゲーマーの登場や、Youtubeのゲーム実況などによって、職業になりました。
無駄だと思われたことが変化したわけです。
そういう意味で、本当に無駄なものは無いかなと。
また、話の中で、大量の消費+大量の情報によって、深みがでるという話もありました。
これもそうですね。専門的な知識は、やはりそれ相応の時間を費やさないと身につかないですし。
記号化
個人的に面白かったのは、記号化という話。
記号化というと、ちょっとわかりにくいですね。
端的に言えば、テンプレ化というのが一番近いかなと。
テンプレ化されることで、消費しやすくなっていくというのと、二次創作も記号化では?という話がありました。
また、少し前の近代文学は、記号化に抗った時代で、現代はどんどん記号化に向かっているという話。
で、これは個人的にですが、現代こそ記号化に抗っている時代なのかなとも思っています。
個人のニーズが多様化、細分化したことで、新しいものがたくさん生まれているのかなと。
一方で、テンプレ化(記号化)が早くなっているとも感じます。
なろう系なんかがわかりやすいですよね。
いきなり異世界転生からはじまったりしても、問題というか。その部分は物語のメインではないので、サクッと省略というか、時間をかけても意味がないというか。
ただ、一方で、転生する際の理由が重要な物語もあるという話もあって、それはテンプレ化(記号化)の打破なんだろうなと。
そう考えると、近代文学とやっていることは変わらない気がします。
それが昔は文豪と呼ばれる一部の人たちのものだったのが、一般化というか、コモディティ化というか、大衆に広まったというのが、個人的な感覚。
今の時代は個の時代で、共通部分はサクッとテンプレ化して、オリジナリティの部分をより出しやすくなったという気もしますね。
また、AIの登場で量産体制がさらに進む気もしています。
テンプレ化したところは、AIにサクッと任せて、書きたいところだけ書くというか、作りたいところだけ作るというか、そんな感じ。
まだ、これからどんどん洗練されていくんじゃないかなというのが、個人的な見解です。
物語を欲する理由
最後にざっくり物語を欲する理由ついて、
- 人間の好奇心
- 退屈の消費
- 情報の整理と記号化
- 伝えたいという欲求
という感じでまとめていました。
結論というか、その時点までの話のまとめという感じですね。
全体的な感想
個人的には、物語を欲する理由について、さらに深堀りしたかったなあという感じ。
と言いながら、脱線した話題を自分が結構出していたので、仕方ないのですが。
再び話をしたいなあと思いました。
他の哲学対話に比べると、知識ベースの話がいろいろと出てきたので、人によっては理解するのも大変なところがある気はしました。
同じ哲学対話と言っても、かなり違うというか。
と言っても、議論するわけではなく、内容を深めていくという感じなので、どうしてもいろいろな知識の話題も出てしまうのかなと。
今回だと、消費の話の際に、暇と退屈の倫理学の話が出てきて、自分を含め半分ぐらいの方が読んでいたかなと。
このあたりは、向き不向きというか、相性もある気はしました。
以下は個人的なメモ
物語の本質は、信者を増やすことなのでは?
テンプレを知ることが、学習では?
何も得るものがないものは、何も得るものがないという情報を得ている。
人はネタバレしか買わない。つまり、得られるものがわかっているから、買う。みんなが買っているから面白いのだろう。同調による安心。共感。もしかすると、情報のズレを補正しようとしている?
