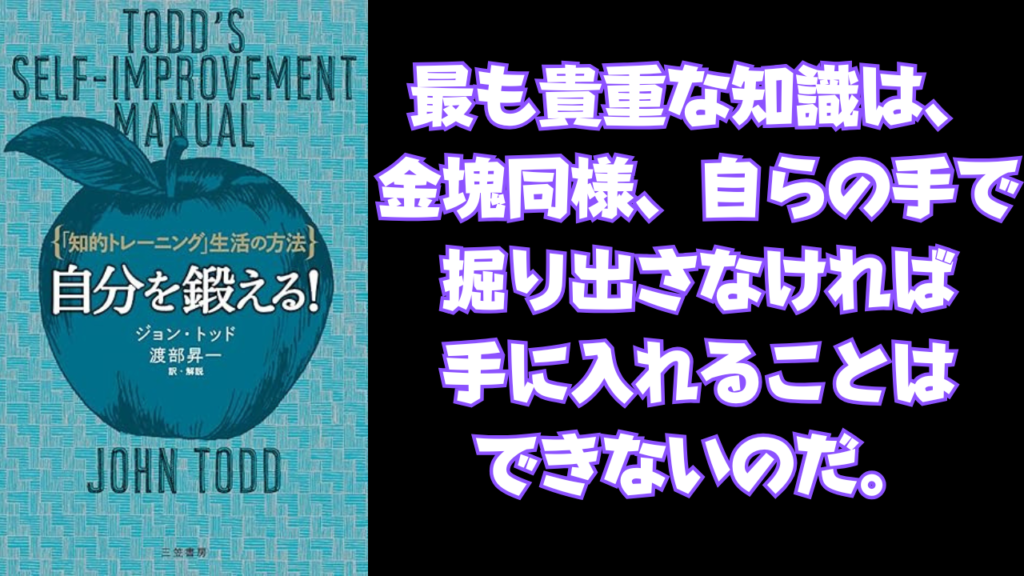
目次
評価・レビュー
☆4/5
どうすれば人間の考える力や知識をしっかり増やしていけるか、日々の習慣や本の読み方、話し方、時間の使い方など、自分の知力を上げ、健康的な生活を送るための規律が書かれた本。
ビジネス書などでよく言われていることが、いろいろと詰め込まれており、内容として納得できることが多いと思います。
ただ、これはあくまで個人的な感覚ですが、意識高い系で元から健康で、そもそもがある程度知的レベルが高くないと実践が難しい点もあるかなと。
さらに、読書については「量より質」という点を強調していますが、現代においては、量と質のバランスが重要かなというのが個人的な見解です。
あまりにも時代の流れ、変化が早く、特にIT業界においては、1年前の話は古くて使えないなんてことがザラ。
なので、質にこだわり過ぎると、いつの間にか時代に取り残されてしまいます。
ある程度、情報量を集めた中で、取捨選択しつつ、学びの途中であっても切り捨てて次にいく必要がある知識もあるという話。
逆に、思想書や哲学書、古典などは、じっくりと読むのが良い気はしました。
というのが、個人的な感想です。
以下は、個人的なメモ。
自らの手で知識を掘り起こす
最も貴重な知識は、金塊同様、自らの手で掘り出さなければ手に入れることはできないのだ。
本書では知識という言葉が使われていますが、個人的には知見という言葉の方がしっくりくるかなと。
単純に知識、つまり情報として記憶することに意味はなく、実際に見たり、聞いたり、体験したり、考えたりして得られた知見が大切という話。
頭の中の道具をいつでも使えるようにする
勉学の目的は、あらゆる面において頭脳を鍛えることである。道具のありかを知り、その利用の仕方を知ることである。
これは自分が大学の時に、「情報はすべて記憶する必要は無く、インデックスだけ覚えておけば、必要な時にその本をまた見ればいい」みたいなことを確か先生に言われました。
というのも、近年のテクノロジーの情報量は膨大で、すべてを覚えておくのは難しいため。
学会などに参加したことがある方はわかるかと思いますが、同じxx学会の発表なのに、隣の教室で話している内容でわからないことって多いんですよね。
もちろん、目的とか、結果とかはわかりますが、ロジックとか、原理については、知らないことが多く、すぐに理解できないなかったりします。
ただ、そういう研究をしているというのを頭に入れておくと、全然違う分野であっても、急に繋がることがあるんですよね。
なので、本書の読書は「量より質」とは、まったく逆とも言えます。
当然、自分の専門分野については、深く知るために質を大切にすることは間違いないですが、専門分野だけだと上手くいかないことも多いのが研究だったり。
二兎を得ようと迷う者は〜
二つのうち、どちらを先にやろうかと絶えず迷っている人間は、どちらもやらずに終わるものだ。
迷っていたら、確かに一兎も得られないだろうなあと。
行動することが大切というのは、個人的にもそう思います。
ただ、最近思っているのは、すぐに行動に移す人ばかりだと、それはそれで上手く行かないんだろうなあと。
様々なタイプの人間がいて、社会なり組織なりチームなりが上手く動くというか。
まあ、全員がリーダータイプだったら上手く行かないという話です。
自己評価の甘さ
自分自身の評価になると、誰もが必ずと言っていいぐらい過大評価してしまうものだ。
あくまで自分の場合ですが、若い時は非常に過大評価していましたね。
若気の至りです。
ただ、過小評価するのもあまり良くないかなと。
過小評価して、自信が無ければ、それはそれで物事上手くはいかないので。
結局、バランスが重要ということなのかなと。
やっぱりメモ魔でいよう
頭に浮かんだ考えは、書き留めなければすぐ消えてしまう
全然違う方面ですが、貴志祐介先生のエンタテインメントの作り方 売れる小説はこう書くでもメモの大切さが語られていました。
やはりメモをするというのは、大切かなと。
時間の浪費は過ちか?
時間を浪費するという過ちは、若い時、いや実際には生涯を通して、とりわけ犯しやすい過ちである。
本書では時間の大切さについても語られていて、時間が大切であることは、自分も同意です。
一方で浪費とは最大の贅沢という考え方もできるかなと。
また、何もしていない時間というのも、人間の脳には必要だとされています。
さらに言えば、すべてをロジックで動くというのは、それはもやは機械と一緒。
加えて、効率化を突き詰めていくと、ロボットやAIには今後かなわなくなってくるでしょう。
人間とはロボットやAIと対極にあるものだとするならば、時間の浪費こそが人間の人間たるゆえん、人間らしさなんじゃないかなとも思います。
なので、個人的には時間の浪費について、そこまでネガティブに捉えなくても良いのかなと。
自分自身のことを話す理由
自分のことや自分の友だちのことや自分の業績のことは、できるだけ口にしないことである。さもなければ、誉めてほしいのか憐れんでほしいのか、そのいずれかを期待しているのだと人は解釈する。
自分は結構何でもオープンに話すことが多くて、特に失敗の話を笑い話としてすることが多いです。
理由としては、自己開示をしないと、相手も自己開示してくれないため、どうやっても表面的な話にしかならないため。
本書では人と接する時にも何か学びが無いかを考えよう的なことが書いてありますが、深い話ができなければ、学べることもほとんど無いでしょう。
つまり、相手から多くの学びを得るには、まず自分のことを話す必要があるということです。
業績については、あまり話さない方が良いというのは、自分も同意ですが、ある程度話さないと、信用を得られないというのもあります。
残念ながら人間というのは、現状は社会的な生き物であり、社会で生きていく以上、意識的にせよ無意識的にせよ、肩書を重視してしまうものです。
業績も同様で、何かで成功した人というのは、重要視されます。
それによって相手から情報を引き出しやすくなったり、交渉がしやすくなったりするのは確か。
流石に武勇伝を語りまくるのは違うと思いますが、サラッと話す分には良いかなと。
で、失敗談を交えて話すと、ああ、それだけ努力したり、失敗したからこそ、そういう実績があるのだなと理解してもらえるので、より信用度が高まると自分は考えています。
何も話さず、ただ相手から情報を得ようとしている人のことを、クレクレなんて言ったりしますが、そうなってしまうと、信用は地に落ち、例え知識があったとしても、それを活用できる場はかなり減ってしまうのではないでしょうか。
また、本書では、
考えや意見を対話によって交換し合えるということほど、人間に与えられたすばらしい贈り物はないのだ。
とも書かれていて、対話がちゃんとできる関係って、お互いに信用していないと難しいかなと。
そういう意味で、やはり自分から自己開示して話すことが大切なのでは?と個人的は思います。
冷静に冷静に
挑発に対して冷静に立ち向かう人のほうが、必ず仲間の支持や尊敬を集める。
すぐカッとなって喧嘩腰になるような人間は、放っておけばいい。そういう人間の喧嘩相手はすぐに見つかる。彼以上に強い者があらわれて、あなたよりもうまくやっつけてくれる。口論好きな人間は、一生決闘をし続けなければならない
先日、とある会合で、ある意見を出したら、猛烈にダメ出しされました。
「絶対無い」という強い否定の言葉を連呼していたのですが、「その絶対という根拠は何でしょうか?」と伺ったところ、「絶対は絶対」と言われ、話題を変えることに。
自分自身、思い込みで語ってしまうことも多いので、常に注意はしています。
しかし、往々にして人間というのは完璧ではないので、間違えてしまうことあるなあと改めて気を引き締めたいなと。
また人望が集まる人の考え方では、
反対意見を持つ人を論破したくなるのが自然な衝動だが、本来の目的は相手を説得して賛同を得ることだ。
という言葉があって、相手を説得する際には、冷静に話をして、喧嘩腰にならないことも合わせて行うと良い気がします。
