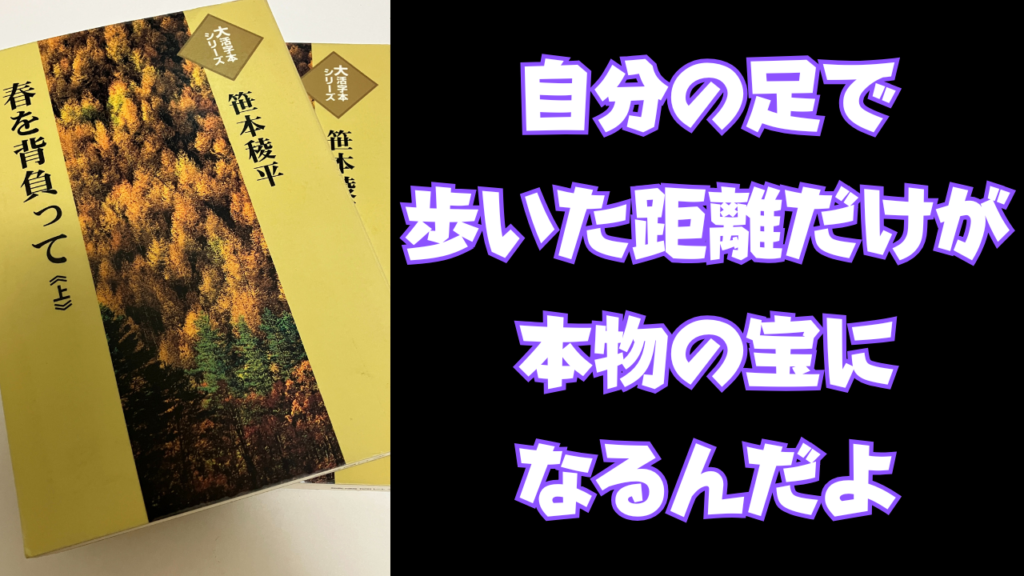
目次
評価・レビュー
☆4/5
サラリーマンだった主人公が、父親が亡くなったことで、父親が運営していた山小屋の経営を引き継ぐことになる。右も左もわからないところに、父親が枕元に立ってよろしくと言われて主人公の手伝いを始める父親の後輩の「ゴロさん」。様々な人間が山小屋に関わり、徐々に変わっていく主人公の生活。そして、父親が山にこだわった理由が少しずつ見えてくるのだった。
みたいな話。
第2回うたたね読書会に参加した際に教えていただいた本です。
山登りとか、山に関する小説ってあんまり読んだことが無かったので、新鮮な感じで読むことができました。
基本的に運動というか、体を動かすアクティビティはあんまり好きじゃないというか、しないのですが、春を背負ってを読んでいたら、山に行くのも良いかなと思ったり。
また、連作短編なので、読みやすかったです。
図書館で借りたのですが、大活字本しかなくて、大活字本自体も初めてでしたが、本が大きいなと思ったぐらいで、読みやすかったです。
以下は本書を引用しつつ個人的なメモ。
死なない程度に衣食足りてりゃ、それ以上の金は要らない
死なない程度に衣食足りてりゃ、それ以上の金は要らないし、他人から尊敬されたところで腹の足しにもなりゃしない。欲はかかない、頑張らない。それが人生を重荷にしないコツかもしれないね。
個人的にも最近そんな感じで思うことが多いです。
お金が無いとできないこと、買えないものってのも一杯あるのですが、今のところ、それらに興味がわかないというのもあるのかなと。
残りの人生を考えた時に、何に時間を使いたいのだろうと考えたら、人と話したり、本を読んだり、文章を書いたり、今だとSunoで曲を作ったりしている方が楽しいというか、そこに時間を使いという感じ。
価値観は人それぞれで、どっちが良いとか悪いとかはなくて、ただ、自分はそうだなあと思ったという話です。
自分の足で歩いた距離だけが本物の宝になるんだよ
つまりね、人生で大事なのは、山登りと同じで、自分の日本の足でどこまで歩けるか、自分自身に問うことなんじゃないのかね。自分の足で歩いた距離だけが本物の宝になるんだよ。だから人と競争する必要はないし、勝った負けたの結果から得られるものなんて、束の間の幻にすぎないわけだ
藤原和博の必ず食える1%の人になる方法で、たしかボランティア的なことをやることで、それが経験になるみたいな話があったかなあと。うろ覚えですけど。
そんな話をふと思い出しました。
つまり、何か目的を達成したいときに、人を使ってやることもできますが、人を使う場合、その目的達成までの経験は実際に行動した人のもので、自分のものではないということ。
自分は結構仕事を何でも引き受けてしまい、ガンガンやっていくタイプなのですが、そのせいで最終的に潰れてしまいました。
ただ、そこでの経験というのは、確かに結構残っているなあと。
で、そういう経験って人に教えても、実践できないことが多いんですよね。
自分の場合、会社を辞める時に、自分がやっていることを全部テキストにして、スクショとかも取って残したのですが、結局引き継いだ人は、それを見ながらやってもダメだったようです。
他にも取引先にやり方を教えろと言われて、同じようにドキュメント化して渡したのですが、うまくいきませんでした。
次の担当の方は、自分の年収の3倍ぐらいあるコンサル系の人で、頭も良いはずなのですが、結局、できなかったようです。
で、それはコンサル系の人の能力が低いわけではなくて、自分は実際にやって経験していて、コンサル系の人は経験していなかっただけということなのかなと。
そういう意味では、苦労は若い時にしろ的な言葉もあながち間違いではないのかもしれません。
そもそも敵なんていなかった
いま思えば、そもそも敵なんていなかったような気がする。勝ち負けでしか自分の力を評価できないから、そのために自分で幻の敵をつくっていたんじゃないのかな
人は1人では生きていけない理由〜アイデンティティは相対的に決まるのかもで書いたのですが、多くの人は他者との相対的な関係において、自分自身を確立しているのかなと思っています。
なので、他者の評価が気になるし、他者よりも上であることに重要性を感じるというか。
で、相対的に決まるというのは、確かにそうなのですが、そればかり気にしてしまうと、逆に自分を見失ってしまうのかなとも思っています。
自分軸を持つことも大切ですが、自分軸しか信じなくなるとそれはそれで問題が起きるというか、悪いことをしても自分自身を疑わなくなってしまうんですよね。
なので、自分軸と相対的な関係の両方が必要で、そのバランスが大切な気がしています。
そもそも、敵を作る必要ってあるのかなってのも自分が思っているところです。
ここでいう敵というのは、自分の方が上であることを示したい相手のこと。
でも、自分の方が上であると示したいと思っている時点で、相手のほうが上なんですよね。
だから、相手を陥れて落とそうとする。自分の方が上なら、別に気にならないですし。
そのあたりに気づくことができれば、他者からの評価というか、他者との相対的な関係による評価が、それほど意味が無いと思えるんじゃないかなと。
まあ、気付かないから、陥れようとするわけですけど。
死にたいなんて思うのは、けっきょく自分のことしか考えていないからなのよ。
死にたいなんて思うのは、けっきょく自分のことしか考えていないからなのよ。
本書で個人的に一番心に刺さった言葉。
まあ、そうだなあと。
自分も死にたいと思うことはしばしばありましたが、結局、自分のことしか考えてなかったように思います。
それは誰かが悲しむとか、そういう話ではなくて、完全な自分本位になっていただけというか。
で、自分本位になっていると、自分の行動が良いのか悪いのかって判断ができなくなっちゃうんですよね。
前述の自分軸とも似た話かなと。
そういうときは、やはり相対的な関係というか、外部からの意見、見え方が必要なんだろうなと思います。
端的に言えば、家族とか友人とか。または心療内科とかカウンセラーとかもそうですね。
その流れで、
人間って、だれかのために生きようと思ったとき、本当に幸せになるものなのかもしれないね。そう考えると、幸福の種はそこにもここにもいくらでもあるような気がしてくるね
というセリフがあって、これも身にしみるなあと。
ただ、自分は特定の誰かのために生きようと思っても、相手がそれを望んでいないのであれば、意味は無いんだよなあというのも、今の自分の実感です。
