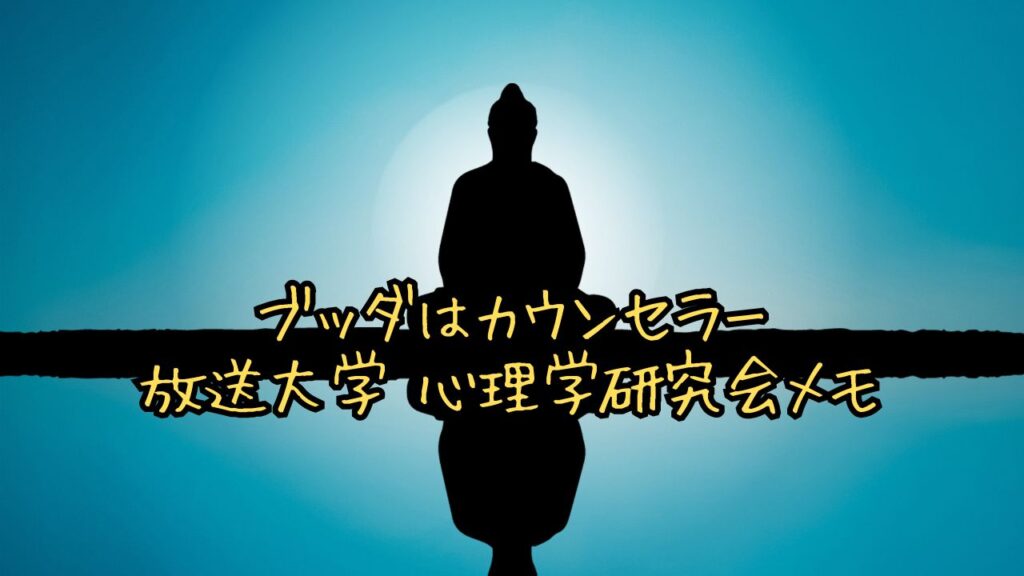
9月の心理学研究会に参加。
研究的な話は無かったものの、いろいろと興味深い話があったので、個人的なメモとして。
ブッダはカウンセラー
まず、ブッダはカウンセラーであるという話。
まあ、細かいことは忘れてしまったのだけれど、結局、多くの人の悩みを取り除いてきたという点で。
また、残っている文献というか、言葉は、弟子との対話で、それによって弟子たちの苦悩が減っているのであれば、カウンセリングになっているという話でもある。
これは、ブッダだけではなく、宗教がそもそもカウンセリング的な機能を持っていると言えなくもない。
人は救いを求め、神にすがる。
そして、何らかの納得を得ることで、不安や苦悩が解決される。
心が平穏な状態になる。
それがカウンセリング的な機能ということ。
写経は考えない、判断しない状態を作る行為
個人的に別な話で、少し考えたのは、写経の効果について。
人は何かを考えるときに苦悩するというのは、よく言われる。
しかし、個人的には考えること自体は悪いことだとは思っていない。
考えることではなく、判断することが、人間の苦悩を生んでいるのではないか?と思っている。
まあ、その話は一旦置いといて、写経をするというのは、一心不乱に文字を書き写すことだ。
で、写経している間は、考えることも判断することもない。
ひたすらコピーをし続けるだけだからだ。
だから、心が落ち着くという話。
で、そういう状態が続くとゾーン的なものに入ることもあるんだろうなと。
また、写経は鉛筆ではダメで、筆じゃないとダメという話があった。
確かに鉛筆よりも、筆で写経するほうが集中力を必要とする。
つまり、それだけ考えること、判断することを捨てることができる。
筆を使うというのには、そのような効果もあるのだろうと思った。
墨をするとリセットされる
写経する際に、墨をする。
その時に、心がリセットされるという。
確かに、墨をするという行為は、日常と写経という非日常を区分けするのに、良い時間を作るような気がした。
つまり、日常と非日常が連続していないということ。
この非連続性は、集中するときに必要な行為というか、必要な要素ではないか。
瞑想はまさにその非連続性を生み出す行為なのではないかとも思える。
子どもの心を開くには母性が必要?
また全然違う話なのだが、子どもが心を開くには母性が必要なのではないか?という話があった。
個人的には、母性、父性というのは、あくまで役割的なものであって、男性だから女性だからというのは、考えていない。
つまり、母性の機能が果たせれば、母性を持っていることになり、父性の機能が果たせれば、父性を持っているという考え。
で、母性って何だろう?というのはふと思った。
なんとなく、母親、女性みたいなイメージがあるが、その本質は一体何なのだろうなと。
これはまた改めて考えてみたいと思う。
