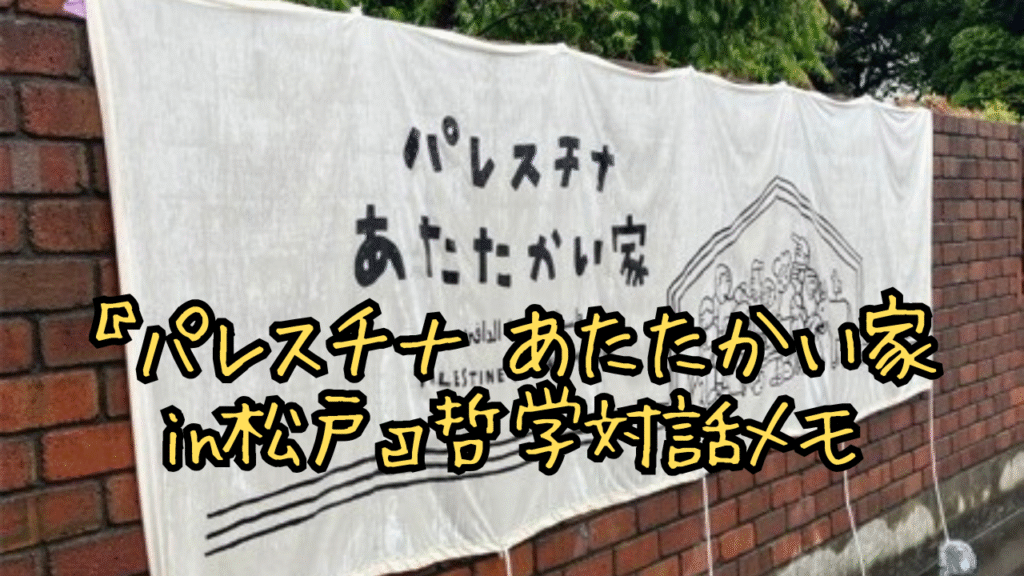
パレスチナ あたたかい家 in松戸で開催された哲学対話に参加した時のメモ。
ファシリテーターは永井玲衣
ファシリテーターは、水中の哲学者たちの永井玲衣さん。
ざっくりルールのメモ。ニュアンスとかはちょっと違うかも。
- まず聞く。
- 対話、言葉で繋がろうとする。
- 暴力を振るわず。
- 問いが育っていく。
- へたな感じでしゃべりたい。
で、最初にそれぞれのニックネームを決め、問い出しフェーズへ。
問い出し中に対話のような感じなっていたのですが、「問い出しが対話形式になってもOK」というスタンスなので、そのまま続行。
この対話形式の問い出しというのも、永井玲衣さんの哲学対話ならではな気がします。
問い「偏っているってどういうこと?」
以下は、問いから、出た意見などを個人的にメモしたものです。
偏っていると言って相手の意見を封殺する、されることがある。
偏っていると言う人は、相手の言葉を聞いていない気がする。
また、聞いたことがないことについて、偏っていると言いがち。
偏っていると言って話を終わらせようとする人は、意見を聞く気がない気がする。
偏っているとは、傾けている。視線を向けている。エネルギーを注いでいる。
偏っているとは、許容量がない、意見を譲らない。許容ができない。
子どもに爆弾を落としたくないのは、偏った考えではないのか?
偏っている人と無理に対話しなくても良いのではないか?
偏っていると言われても、気にならない。それは、選択肢が用意されていて、自分で選択肢を選んでいるから。
つまり、選択肢があることが大切で、選択肢がないものを信じているのを偏っていると言うのかも。
熱量がある活動において、その人の中に自分が存在できないと感じたとき、偏っていると言うのかもしれない。
xxさんが好きな人が自分の中に存在させられないとき、偏っている。
きのこの山、たけのこの里論争と戦争の違い
チョコとクッキーはみんな好き。共通の好きをベースに議論しているから、戦争にはならないのではないか?
→個人的にですが、この共通の好きがベースになっているというのは、とても大切な考えだなと思いました。おそらくですが、争いが起きた時に、共通の好きを最初に見つけておくことで、甚大な被害が起きることを防ぐことができるのでは?ということです。
命とどれだけ関わっているかが重要ではないか?
→イスラエル・パレスチナ紛争において、我々の命がすぐに脅かされることはありません。他者の命であっても、同様に重く考える場合、他の地域の難民や飢餓で苦しんでいる人は放っておいてよいのだろうか?という疑問がでてきます。さらに、近年ではアニマルライツなどの考え方も広まっており、地球上の生命全体の責務を、個人が背負うことって難しいのでは?とも思います。このあたり、もう少し深く話を聞きたかったなあと。
個人的な考えメモ
話を聞いていて、個人的に考えたことなど。
そもそも偏ってない人なんていないかなと。
なので、多くの意見を集めて、それでバランスを取るしか今はできないと考えています。
母集団の取り方や、サンプル数をどうするかは、ちゃんと考えないとなーみたいな。
なんか統計的な話になってますが、そもそも偏っているかどうかは、ちゃんとデータを取らないとわからないだろうなと。
あと、偏ってない方が正しい? 偏っていると言うのが、悪い? というのもちゃんと考えたいなと思いました。
個人的にポジションの問題でしかなく、また参照点(中心点)の置き方でも変わってくるだろうなとも思いますし、平均を取れるなら、その平均がわからないと偏っているとは言えないかなとか。
加えて、偏っているように見えるのは、距離が離れているからで、逆の視点も一緒だなあと。
という話を、帰りにご飯を食べている時に友人に話したら、相手から見えている距離が一緒とは限らないという指摘がありました。
確かにその通りだなあと。
主観なので、相手との距離感は本人にしかわからないということ。
近くに感じていても遠かったり、遠くに感じていても近かったりという話です。
てか、距離が遠いと感じているなら、別に関係性が切れても問題ないとは思うんですが、どうなんだろうなとは思ったりしました。
余談
今回の哲学対話に参加するにあたって、本を4冊ほど読みました。
できれば、イスラエル側の論理、パレスチナの論理の双方の視点を知りたかったからです。
ただ、現状では、中立の視点で書かれている本は少ないかもなあとか。
少なくとも自分が呼んだ本は、どちからというと、パレスチナ側のものが多かったです。
それでも、オスマン帝国時代から書かれていた本については、かなりわかりやすくて勉強になりました。
というのも、オスマン帝国の時代では、パレスチナにユダヤ人もパレスチナ人も一緒に住んでいたんですよね。
で、自分が思ったのは、イスラエルとパレスチナって、昔は戦う理由が無かったんだよなあということ。
それが、イギリスの三枚舌外交や世界大戦などいろいろとあって、今に至っているという感じ。
そんなことをぼんやりと思いながら、哲学対話に参加していて、で、きのこの里、たけのこの山の話から、共通の好きがベースにあると、戦争までは至らないという話を聞いて、ああ、そうかもなあと。
イスラエルとパレスチナの紛争は、解決が難しいと言われています。
ただ、難しいかもしれませんが、お互いの好き、大切なことを共有して、対話を通して共通点を見つけることができれば、歩み寄れる可能性もあるんじゃないかなって。
戦争って、結局要求と要求のぶつかりあいで、お互いに相手が悪い、相手の意見を聞かない状態です。
ではなくて、まずは相手の話を聞くこと、相手と対話することが大切なんじゃないかなって。
ただ、相手が対話を望んでいなければ、どうしようも無いんだよなあと。
どうしたら、相手が対話のテーブルについてくれるのか?というのが、自分の今の目下の悩みです。
対話を拒否されると、どうしようも無いんですよね。
