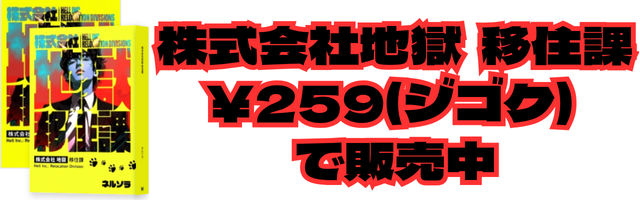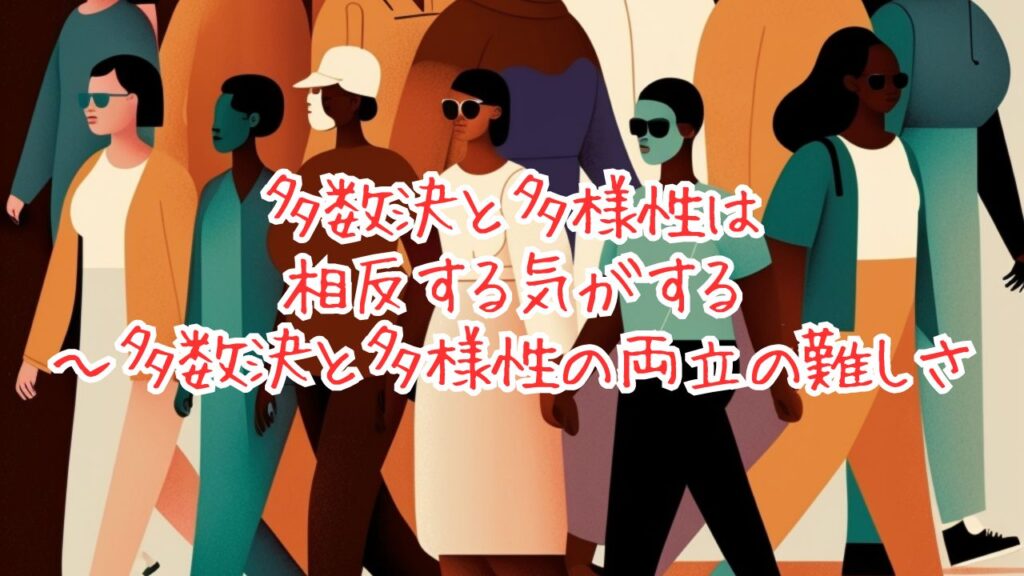
書き殴った文章をAIに整理してもらった。
目次
多数決と多様性は両立しにくい
多数決とは、マジョリティ(多数派)の意見を採用する仕組みであり、
多様性とは、マイノリティ(少数派)の意見を受け入れる姿勢である。
したがって、この二つを同時に成立させることは本質的に難しい。
多様性を主張するということは、ある意味で多数決という仕組みに異を唱える行為でもある。
多数決のメリットと特徴
多数決は「最大多数の最大幸福」を目指す仕組みとも言える。
結果としてより多くの人が幸福を感じやすく、仮に失敗しても責任を多数で分担できる。
また、単純に過半数で決定できるため、物事を迅速に進めやすいという利点がある。
多様性の難しさとジレンマ
一方で、多様性を重視する社会は、マイノリティの意見も尊重するため、
決定を下しにくく、物事が進みにくいという問題を抱える。
さらに、他者の意見を受け入れることは、
自分にとって不快なものや不利益なものも容認することを意味する。
本気で多様性を実現しようとすればするほど、
合意形成に多大なエネルギーが必要となる。
「なんちゃって多様性」という現実
表面的な多様性――いわば「なんちゃって多様性」――も多い。
たとえば企業では、ジェンダーの異なる人材を雇うことで多様性を実現したとする場合がある。
しかし本来の多様性とは、性別や属性に限らず、
立場や意見の違いをも尊重することである。
経営陣の意見しか通らず、社員の声が反映されないのであれば、
それはマイノリティの排除であり、多様性の否定にほかならない。
富と多様性の関係 ― 再分配の必要性
多様性を本気で担保するなら、富の再分配も避けて通れない。
たとえば「働きたくない」という人の意見も尊重するなら、
彼らが生活できるような**仕組み的サポート(再分配)**が必要になる。
もしそれを否定するなら、「働きたくない人」は多様性から除外すべき対象として
明確に宣言する必要がある。
「多様性」を唱える人々への問い
結局、多様性を強く主張する人々の中には、
本気で多様性を実現したいというよりも、
「多様性」という言葉を自分たちの利益のために利用している場合もある。
特に「ジェンダー多様性」だけを語る場合は、
「多様性」ではなく正確に「ジェンダー多様性」と呼ぶべきである。
決定の仕組みをどうするか?
多様性を掲げる社会では、決定のルールを明確にする必要がある。
多数決なら「過半数で決定」とシンプルだが、
多様性は「全員の合意」が必要なのか、それとも別の基準があるのか不明確である。
どの意見を採用し、どれを退けるのか。
その線引きや基準を明確にしない限り、
多様性は結局「上司や権力者の裁量」に依存することになる。
結論:多様性は理想だが、実現は困難
多様性は理想的な考え方だが、
実際に運用しようとすると、決定の遅延・責任の不明確化・基準の曖昧さといった課題が伴う。
最終的に言いたいのは――
**「多様性って、本当に難しいよね」**ということである。
以下、AIにまとめて貰う前の原文
多数決とは、マジョリティの意見を採用するということ。
多様性は、マイノリティの意見を受け入れるということ。
つまり、この二つを同時に成立させることは難しいのだ。
多様性を主張するということは、多数決に反対することでもあるという話。
多数決というのは、ある意味、最大多数の最大幸福を目指しているとも言える。
まあ、確実に最大になるかは別として、より多くの人の幸福が得られやすい。
結果、失敗したとしても、多くの人たちで責任を分担できる。
多様性の場合は、みんなちょっとずつ幸福になって、みんなちょっとずつ不幸になろうみたいな感じにも思える。
なぜなら、お互いの考えを受け入れるということは、自分にとってメリットが無かったり、不快だったりするものを容認しなければならないからだ。
多数決は決定を下しやすいため、物事を進めやすい。単純に過半数を取れば良いから。
多様性は決定を下しにくいので、物事は進みにくい。なぜなら、マイノリティの意見もすべて聞く必要があるからだ。
また、多様性においては、反対意見も組み入れなければならない。だから、ちゃんと物事を進めようと思うと、かなり大変と言える。
あくまで、ちゃんと多様性を実現しようとする場合だけど。
なんちゃって多様性であれば、とても楽だ。
例えば、会社組織を考えた場合、なんちゃって多様性は、今だと、様々なジェンダーの人を雇えば実現できる。
しかし、多様性とはジェンダーのことだけではない。
だから、会社の場合、一社員の意見も経営者がちゃんと聞いて、それを経営に反映する必要がある。
経営陣だけの意見しか採用しないのであれば、マイノリティの意見を弾圧しているのと変わらない。
会社組織は別だろうという意見もあるだろう。
ということは、会社組織は多様性から除外すべき対象であると、多様性を主張する人たちは宣言すべきだ。
また、富という点では、多様性を考えるのであれば、かなりの再分配が必要になると自分は考えている。
多様性を担保するということは、働きたくない人の意見も聞かなければいけないわけで、働きたくない人は生活するのにお金が必要だから、彼らの意見を聞くために富の再分配をする必要がある。
もし富の再分配をせず、働きたくない人の意見を封殺するのであれば、それは多様性ではない。
もちろん、働きたくない人は、多様性から除外すべきだという考えもある。
であるならば、多様性を主張する人たちは宣言すべきだ。
働きたくない人の意見は聞く必要が無いと。そんなマイノリティの人間の意見は意味が無いと。
結局のところ、何が言いたいのかというと、多様性多様性と声高に叫んでいる人たちの多くは、多様性を実現したいのではなくて、多様性と言うことで、自分たちにメリットがあるから、多様性と言っているだけなのではないかという話。
または、ジェンダーの多様性だけを議論にしている場合もある。
であるならば、多様性ではなく、ちゃんとジェンダーの多様性と言うべきなのではないだろうか。
それであれば、納得できることも多い。
あと、多様性を主張するのであれば、決定の下し方についても、明確な指針が必要ではないだろうか。
多数決は過半数を取ればOKだ。
多様性は、全員の合意で合っているのだろうか?
それはかなり難しいだろう。
じゃあ、どうやって線引するのか。
どの意見を採用し、どの意見を不採用にするのか?
その基準はどこにあるのか?
何を基準にするのか?
結局、上司が決定しているだけではないのか?
このあたりの、決定システムについても、多様性を主張するのであれば、考えて起きたいところだなと思ったり。
何が言いたいのかというと、多様性って難しいよねってこと。