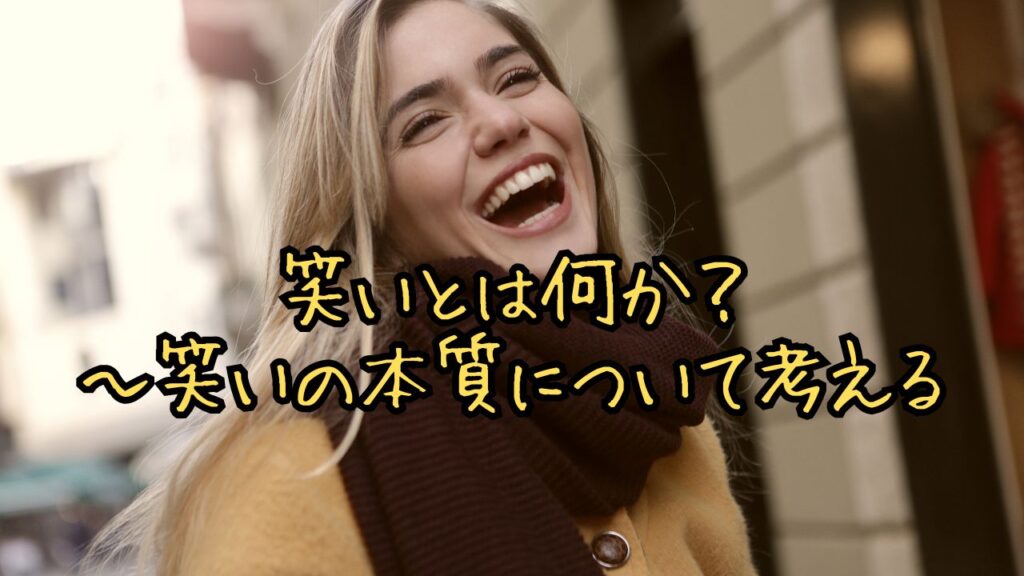
個人的に、面白いとは理解だと考えて、笑いと面白いを区別して考えている。
面白いから笑いになることもあるが、笑えるから面白いというわけではないため。
ただ、理解が無いと、笑いは発生しない気がしている。
で、笑いとは何かについていろいろと考えてみる。
目次
笑いとは優越感の理解
まず最初に個人的に考えているのは、「笑いとは、相対的に自分が優越感を感じることができる、優越感を理解できることが重要なのではないか」という点。
バカらしい行動を見ると、面白い、笑えるというのは、相対的に自分はバカではないことを感じることができる、理解できるから。
イジるのが笑い(面白い)されるのは、相手を下げることで自分自身の優越性を理解できるため。
イジメが面白いと感じてしまうのも、まさに自身の優越感を満たすことができるからではないか。
優越感の理解。優越感に浸れることとはちょっと違うかもしれないが、そこに面白さ、笑いの本質がある気がしている。
アンジャッシュの渡部さんが不倫の件でイジられるのを見ていて面白いのは、結局もともと自分たちよりも上だと思っていた人が、落ちていくことで、自分たちよりも下だと認識できる、つまり優越感を感じることができるからという感じ。
笑いとは違いの理解で不安の解消
いとをかし。
可笑しい。
可怪しい。
おかしいとは、面白くて笑い出したくなる気持・有様だ。こっけいだ。
このおかしさとは、異質である、普通とは違う異なるという意味。
ただ、普通とは違うだけでは、おかしいにはならない。
そこに理解が必要だ。
理解できるから、違うことが認識でき、そこに不安がなくなる。
おかしいには、例えば何かがおかしいという使い方がある。
漢字にすれば、可怪しい。
このおかしいは、それが何かわからない状態なため、不安が生じていると考えられる。
逆に言えば、不安とは情報を理解できない状態とも言えるかもしれない。
不安を解消することが幸せであり、楽しいであり、嬉しいであり、笑いなのかもしれない。
ボケとツッコミの役割
まさにボケることで、異質な状態を作り、ツッコミを入れることで、それが異質な状態であると、観客に理解させている。
異質であることが理解できれば、可笑しいし、面白いし、笑える。
ボケたとしても、それが異質であることが理解されなければ、笑えないだろう。
つまり、ボケとは異質な存在を演じる役割で、ツッコミとはそれを視聴者に伝える役割と言える。
面白さは分類できる
頭がおかしくなるという表現がある。
自分の頭が周囲の人の頭、または通常の自分の頭の状態とは異なる状態になっていることを認識している状態。
当たり前のことを当たり前のように言うのは面白くない。
知っていることは、理解する必要が無いからだ。
今までになかった視点が出てくると、そこに面白さを感じる。
何が言いたいかというと、面白さは、何を理解するかで分類できるのではないか?ということ。
知識としての理解は、新たな知識を得ることで自分のレベルが上がり面白さを感じる。
その人が馬鹿であることの理解は、他者を下におくことで自分のレベルが上がることで面白さを感じる。
こんな風に、どんな情報かを理解するかで、面白さは分類できる気がする。
自分のレベルが上がるとは、自身の優位性の確保か
理解することは自身のレベルが上がるということが根源にあるのではないか?
という考え。
人間は生命体、利己的遺伝子、つまり、自身が他の人間よりも優秀な種であることを示す、または自身が優秀であると認識することで、種としての本分を全うできる。
人類の進化には理解が必要だった。
つまり、理解するとは、自身が種として優れていることの現れ。
知ったかぶりとは、種の優位性を保つための行動か
知ったかぶりをするのもそう。
知らないということは種としての劣っていると認めること。
しかし、知らないことを知らないと言える人もいる。
それはその知識への理解が種としての生存に役立たないと考えているからではないか。
それは個体差なのかもしれないし、年齢的なもの、つまり、経験によって得られた知見かもしれない。
また、社会的にも知ったかぶりをすることが、劣った人間であるという認識ができつつあり、知ったかぶりをしないことの方が優れた人であるという評価がもっとされていけば、変わっていくだろう。
つまり、知ったかぶりをしない方が種として優れている、種としての生存戦略として正しいと認識するということだ。
種の生存戦略としての正しさとは
この正しさについては、本能に刻まれていることではなく、知性が関係しているのはないかとも思える。
それは、馬鹿ということではなくて、単純に知性を重視するプログラムと本能を重視するプログラムという違いなのではないか?
右に進むべきか、左に進むべきか迷った時、知性を重視するプログラムは情報を集めて判断を下す。
本能を重視するプログラムは、捉えた感覚から判断を下す。
情報があったとしても、それが正しいかどうかを判断できない場合、例えば偽りの情報だった場合、知性を重視するプログラムは選択ミスをする可能性がある。
何が言いたいかというと、何かを選択する際に、全員が同じ選択をしないようにするために、そのような違いが生まれているのではないか?ということだ。
映画などでよく頭でっかちの人間がすぐ死んでしまうことがあるが、それは単純に頭でっかちでは駄目ということではなく、頭でっかちの選択が常に正しいというわけでないということを示しているという話。
それは人間が本来持っている本能による選択をする余地を与えている、余地を残しているということなのかもしれない。
笑いとは
と、話が大幅に脱線した感はあるが、結局、何が言いたいかというと、
「笑いとは、自身の優位性の理解によって発生する安心感」
なのではないか?ということ。
理解と言うよりも、認知といったほうが良いのかも知れない。
というのも、周囲が笑っていると、つられて笑うことがある。
それは、対象に対して笑っているのではなくて、雰囲気や周囲の人に共感して笑っているということで、面白さを理解していないこともある気がするからだ。
ただ、それは笑いの本質では無い気がする。
やはり、笑いは優位性と安心感が関係しているのではないだろうか。