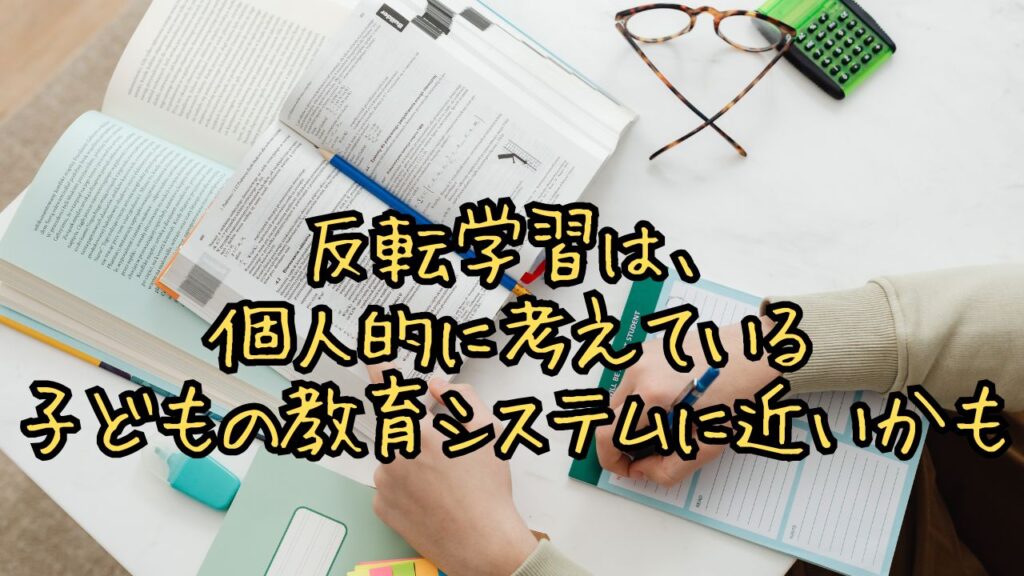
反転学習とは、ざっくり言うと、「授業で学び、自宅で復習する」という流れを反転させて、「自宅で予習し、授業で実践」するというもの。
個人的に考えていた教育システムは、家で学習し、学校では討論、問題解決、わからないところを聞くという感じなので、ほぼ一緒かなと。
学校の授業で一方的に教えるのって、どれほど意味あるのかな?というが、考える出発点。
自分の場合、授業よりも教科書をざっと読んだ方が効率が良いと思っていて、それは学校じゃなくてもできる。
実際、今年、放送大学の授業を取ったのだが、講義動画の授業を2本ほど見て、本読んだ方が速いと感じ、講義動画は観なくなってしまった。
講義動画は、12時間分あるけれど、本なら4〜5時間ほどで読めてしまう。
なので、同じ12時間で考えると、本なら2回知識を入れること(入力)ができる。
その分、知識の定着率も高い気がしている。
また、実際に小中学校などに、反転学習的なシステムを入れると、教師の負担が減るだろうなと。
教師は無理に授業用に何か準備する必要が無くなるから。
基本的に学習は、生徒同士で進めていき、わからない点などを先生に聞くという流れのため。
子どもたちにとっても、自分のペースで学べるというのが大きい気がする。
ある程度、学んでいる部分に違いがでたら、それを元にクラス分けするという手もある。
ちょっとした飛び級制度みたいなもの。
それを学年ではなくて、学校全体としてシステム化しても面白いかもしれない。
ある程度、学び終えテストに合格したら次のクラスに進むみたいな感じ。
卒業に差がでるけれども、それのデメリットが個人的はあまり見つからないかなと。
それよりも、学校全体としてシステム化した場合、学習ペースが遅い人を置いていくことが無くなるので、全体の学力のベースアップに繋がる気もする。
まあ、そこで、差別的なものが生まれる可能性はあるけれど、今だって特進クラス的なものは存在しているし、その点について、ちゃんと子どもたちに説明すれば、差別も起きにくいのではないだろうか。
クラスの変更は年ごとではなく、もっと短いスパンにすれば、子どもたちがクラス内で群れにくくなる気がする。
それによって、集団によるいじめが起きにくくなるかもしれない。
友達などができないことが問題にされるかもしれないが、それは部活などの活動でも補完できる気がする。
むしろ、クラスがちょこちょこ変更になれば、多様な人と関わることができるので、コミュニケーション能力は高くなりそう。
というのも、今の時代、社内での飲み会も減り、社内恋愛も少なくなっていて、会社内での仕事以外の繋がりが弱くなている。
皆に聞きたいが、社内に友達は一体どれほどいるだろうか?
個人的にはほとんど友達といえる人物は作れなかった。もちろんいないわけではないけれど。
それよりも社外での友達の方が圧倒的に多い。
だから、小中学校でも同じような状況になっても、問題無い気がする。
塾だってあるし。
また、知識の定着という意味では、プログラム学習的なもので対応するというのが良い気もする。
ネット経由で自分でテストを受けていく感じ。
これによって自主性も高まるのではないか。
勉強させるのではなく、自分で勉強していくというクセを付けるのが、そもそも学習において重要ではないだろうか。
知識を身につけることではなく、わからないことを自ら率先して学ぶことが大切ではないだろうか。
自習型は、内的動機づけでもあるので、学習効率も上がりそうな気もする。
まあ、何にせよ、今の小中学校の教育システムについては、再考が必要な気がしている。
それも抜本的に。