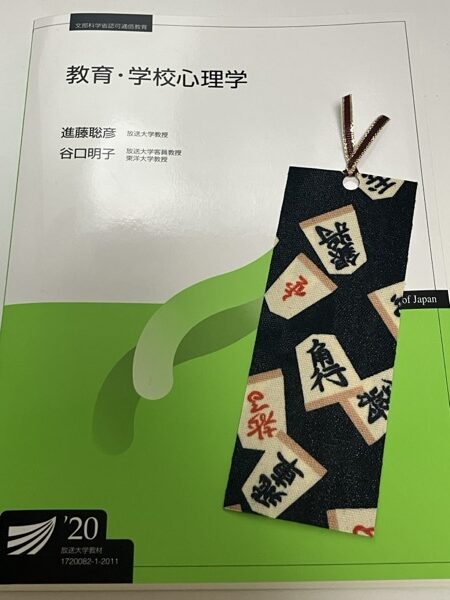
評価・レビュー
☆5/5
教育心理学、学校心理学とは何かからはじまり、研究法や教科学習など解説、子どもたちの学習方法や自律的学習ができるようになるための育成方法、教師に求められる資質、学級などの集団における教育、障がいがある子どもたちにおける状況や学習のあり方など、かなり多岐にわたって書かれているのが特徴です。
個人的に一番興味深かったのは、道徳性の育成。
年齢がアップしていくにしたがって、良いこと(善)の捉え方というか、なぜ悪いことをしていけないかの理由が変わるというのが衝撃でした。
紹介されていたのは、コールバーグによる道徳性の発達段階というのもので、6段階あるのですが、大人であってもこの6段階目まで発達している人ってどのぐらいいるのかな?と思ったからです。
例えば、人に濡れ衣を着せるという行為。
誰がどう考えても、悪いことです。
で、ここで重要なのは、なぜそれが悪いことなのか?ということ。
もちろん、人に濡れ衣を着せているわけですから、迷惑をかけているので悪いという人はいると思います。
じゃあ、悪いことととは、人に迷惑をかけることという定義で良いのでしょうか?
人に迷惑をかけなければ、何をしても良いのでしょうか?
それを明確に答えることができる人って、少ない気がするんですよね。
それは善悪の定義が自分の中でしっかりと定まっていないからだと思います。
以前、とある番組では、善とは何か?という問いに、コメンテーターの人が「善とは善いことです」と答えていました。
「善いことって何?」という問いに、「善いことは善いこと」という回答。
本書を読んでいて、その時のことを思い出し、少し怖くなりました。
だって、善の定義が定まってないからです。
なぜなら、このコメンテーターの人の中で、善だと思えば善ということになってしまうため。
極論を言えば、理由付けさえできれば、それで自分を騙すことができれば、犯罪も善になりうるということです。
で、それを愚か者だと嘲笑することは簡単ですが、果たして、「善とは何か?」という問いにちゃんと答えられる人は、一体どのぐらいいるんだろうなあと。
そのぐらい社会というのは、意外と脆いところがあるというか、綻びが存在するというか、あやふやで曖昧なところがあるような気がします。
また、個人的には善の定義を持っていますが、それが正解かどうかってわからないんですよね。
ただ、少なくとも社会全体として、ある程度皆が納得できる答えは持っておいた方が良い気がしました。