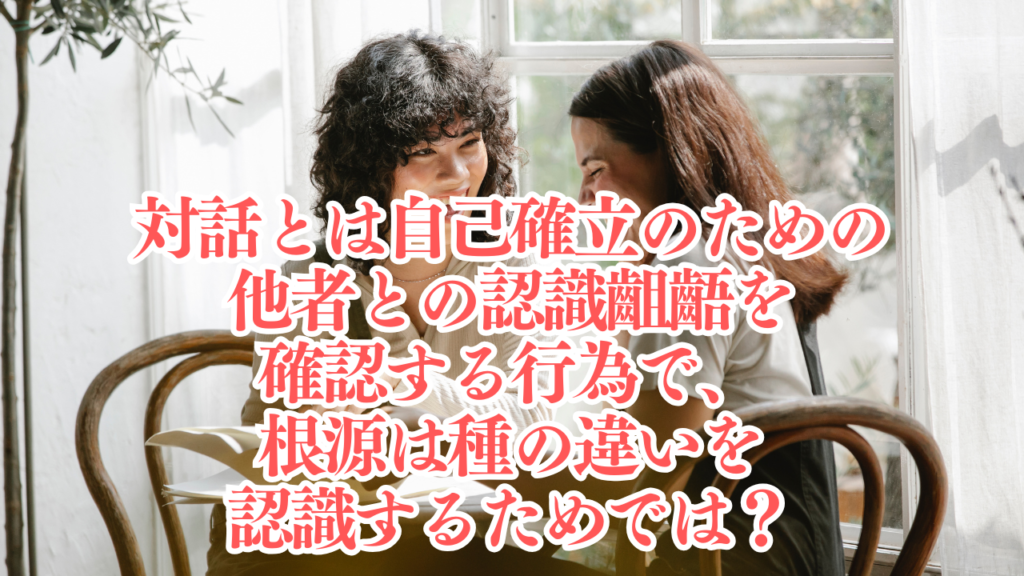
思ったことをつらつらと。
対話とは
一般的に対話とは
向かい合って話し合うこと。また、その話。
対話(たいわ)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説 – goo国語辞書
みたいな感じかなと。
対話の目的とは
その目的は、
- 相互に理解を深める
- 落とし所(解決策)をみつける
という感じでしょうか。
個人的な対話の定義
人は1人では生きていけない理由〜アイデンティティは相対的に決まるのかもで、対話する理由として「他者と対話することで、相対的に自分自身が確立されているから」と書きました。
つまり、「対話とは自己確立のための他者との認識齟齬を確認する行為」とも言えるのかなと。
で、これは前述した一般的な対話の目的とはちょっと違うんですよね。
個人的には、あくまで認識齟齬、つまり認識の違いを確認する行為であって、そこに理解や落とし所(解決策)が必要かどうかは関係ないというスタンスです。
会話と対話の違い
個人的にですが、極論を言うと、会話も対話も情報を相互にやり取りするという観点では一緒です。
ただ、対話は自己確立することが目的で、会話にはそれが無いというだけ。
違いを認識するという意味では一緒ですが、会話の目的は情報収集と情報伝達で、自己確立が無いということです。
逆に言えば、何気ない会話であっても、自己確立に繋がるようなこともあり、それは対話になる可能性があります。
言ってしまうと、対話か会話かは、自分自身の捉え方次第とも言えるかなと。
対話の根源
これはあくまで個人的に考えていることですが、対話の根源は生命の仕組みにあると思っています。
生命というかDNAですね。
DNAは自身のDNAを残すために、他の種と自分の種を区別する必要があります。
区別をするためには、自分の情報と相手の情報が必要です。
それが対話の元なんじゃないかなと。
会話も言ってしまえば、同じ線上に並んでいる手段の1つと言えます。
理解して欲しい、理解したい理由
これも推測ですが、人が自分を理解して欲しかったり、他者を理解したいと思うのは、自分という種と相手の種が近いことを認識するためではないか?とも考えられます。
だから、一般的な対話の目的に理解が入ってくるのかなと。
理解することは、お互いに近い存在であることを認識することなのかもしれません。
種として近いことを認識できれば、敵ではないことを認識できるので、そこに安心感が生まれます。
自分のことを理解してもらえれば、自分が敵ではないことを相手に認識してもらえるということで、他者を理解するというのは、相手が敵ではないことを認識することとも言いかえることができるかなと。
敵というのは、端的に言えば、他の種ということです。
人間は複雑だから対話が必要になった
単細胞生物はほぼ一緒の構成なので、会話や対話による情報伝達(コミュニケーション)は単純なもので問題ありませんでした。
しかし、人間は複雑。ここでいう複雑というのは、同じ種なのかをすぐに判別できなくなったということです。
そのため、会話や対話が求められるようになったのでは?というのが個人的に今考えていること。
最初は外見的の違いで、さらに精神的な違いも生まれ、益々対話が求められるようになって来ているのかなと思います。
このあたりは、もう少し整理してから、改めて考えてみたいなと思いました。